今回の記事(補遺)はもともと「ちあり編を語るシリーズ第五回」記事で書いていた内容のうち、テーマから少し逸れるために最終的に採用しなかった部分を、単独記事として再構成したものとなります。
※この記事では、風雨来記4母里ちあり編のネタバレを含みます。
It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.
キツネ「キミがキミのバラの為に費やした時間こそが、キミにとってのバラを、かけがえの無いものにしているってことだよ」
星の王子さまより
「大切なものは、目に見えない」
上記記事の「⑤~目を閉じて感じるもの~付知峡」で書いたとおり、ちあり編では主人公が「視覚を閉じてその場所を感じる」場面が多くあります。
これは、主人公の旅を楽しむための姿勢であると同時に、リリさんが「視覚で他人を識別することができない」ことのメタファーでもありました。
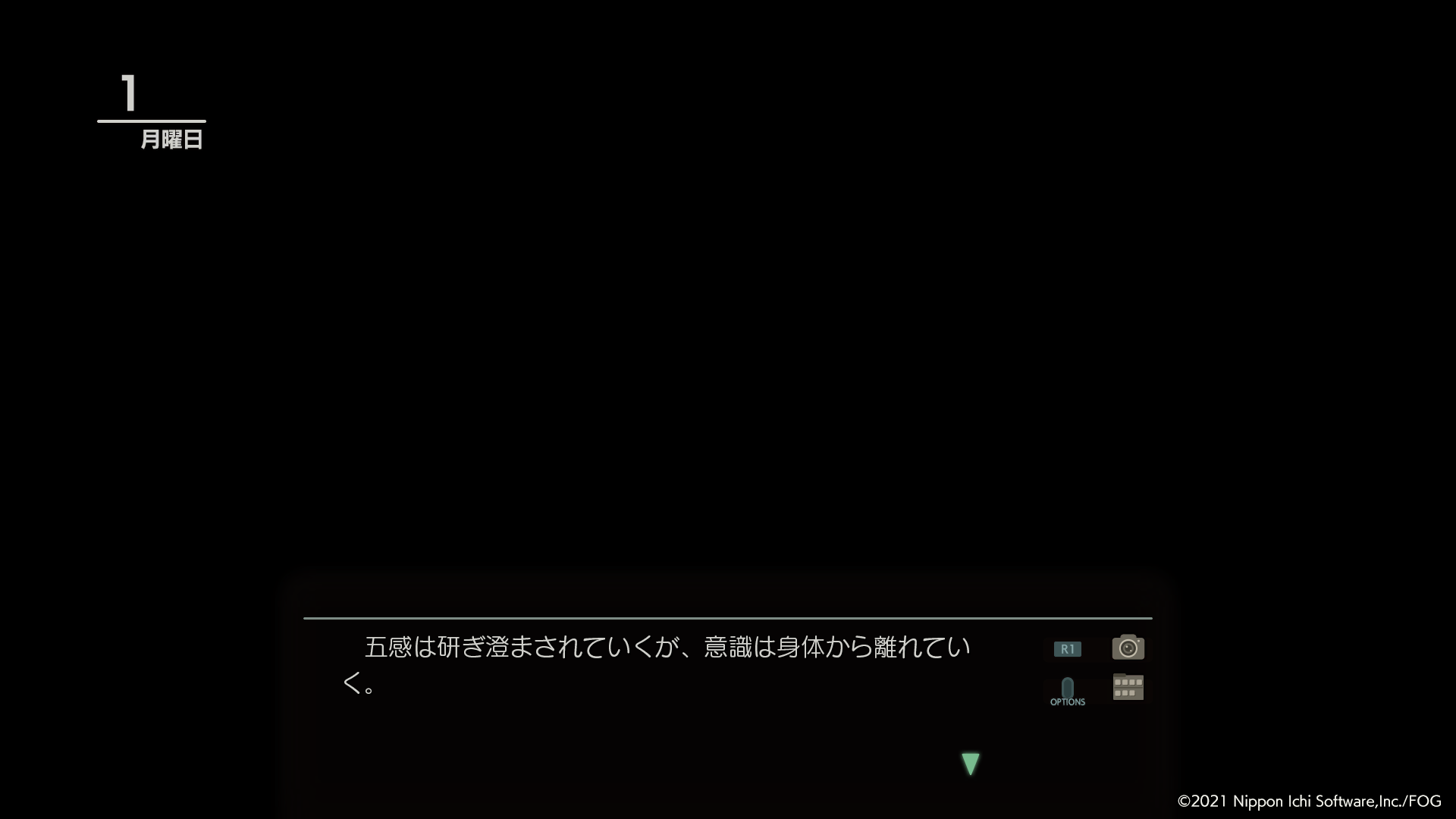
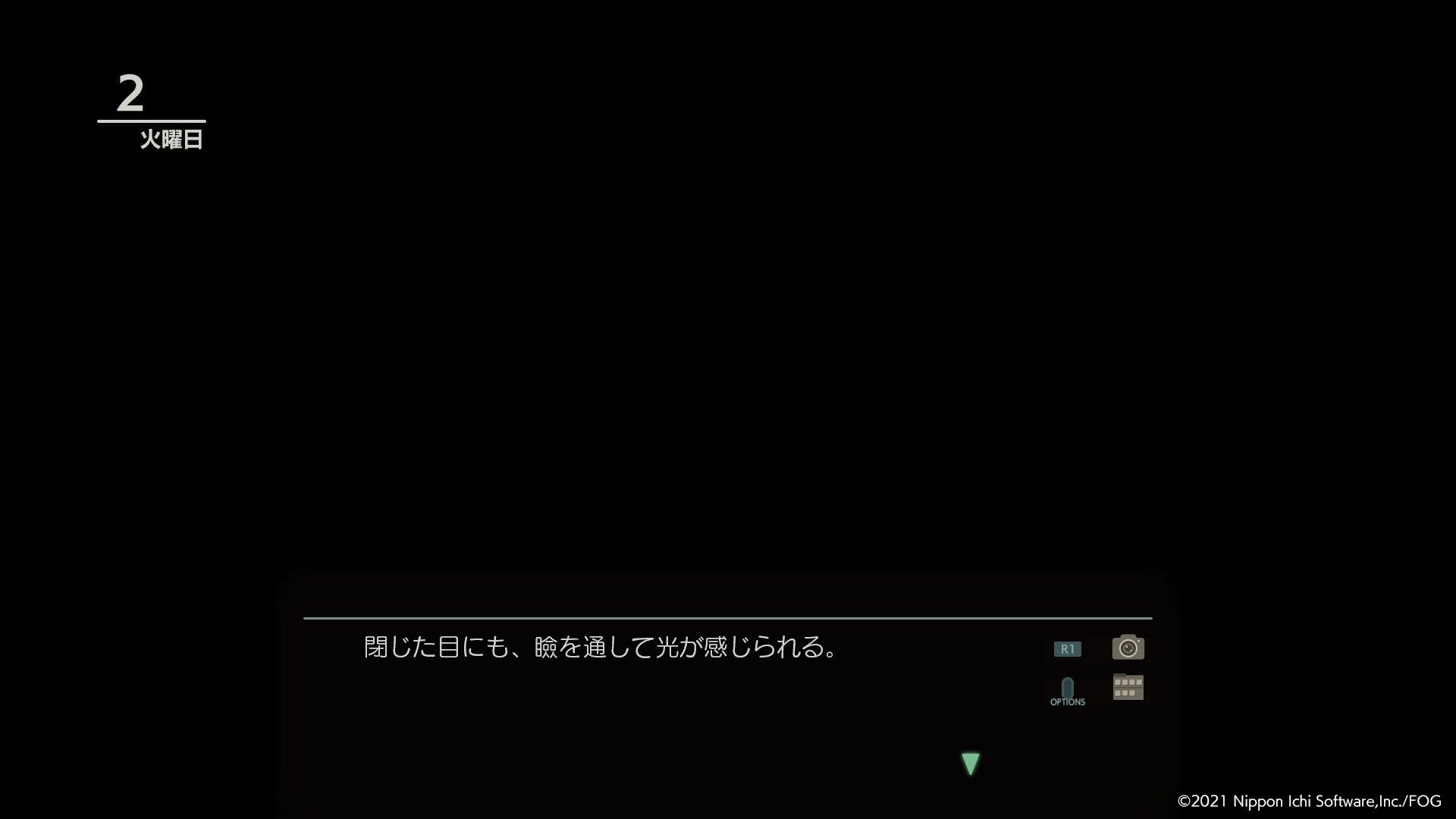
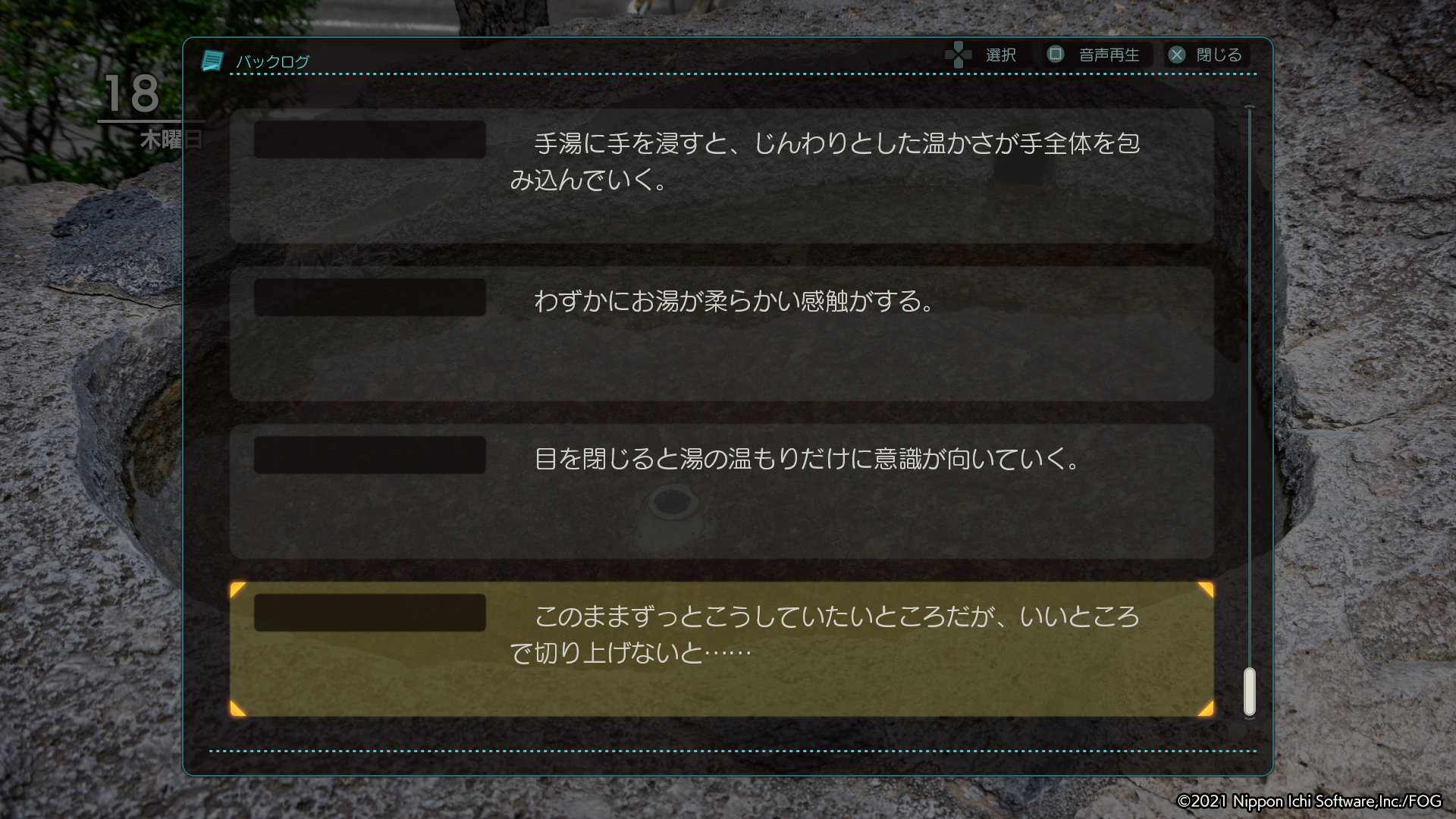
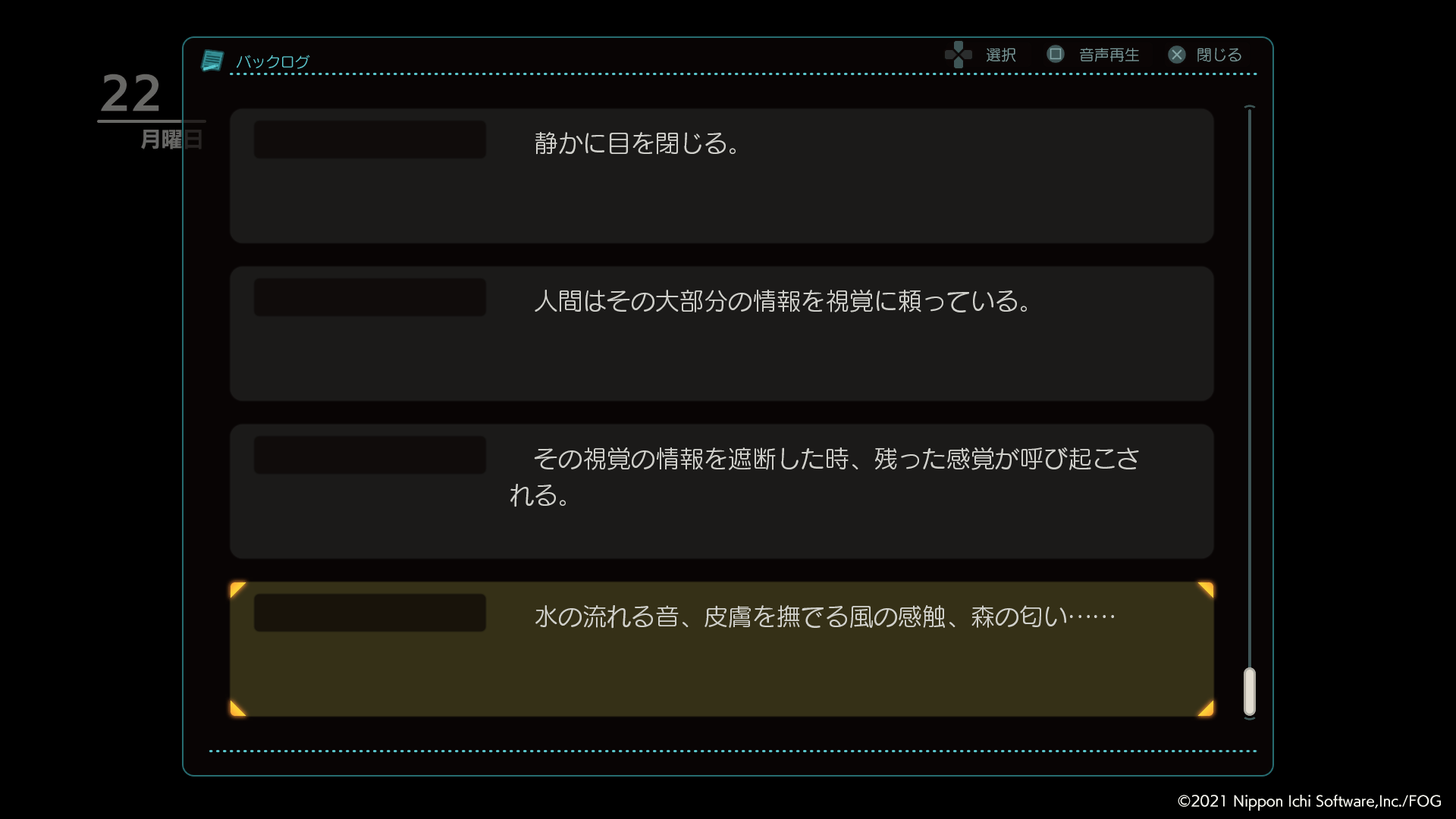
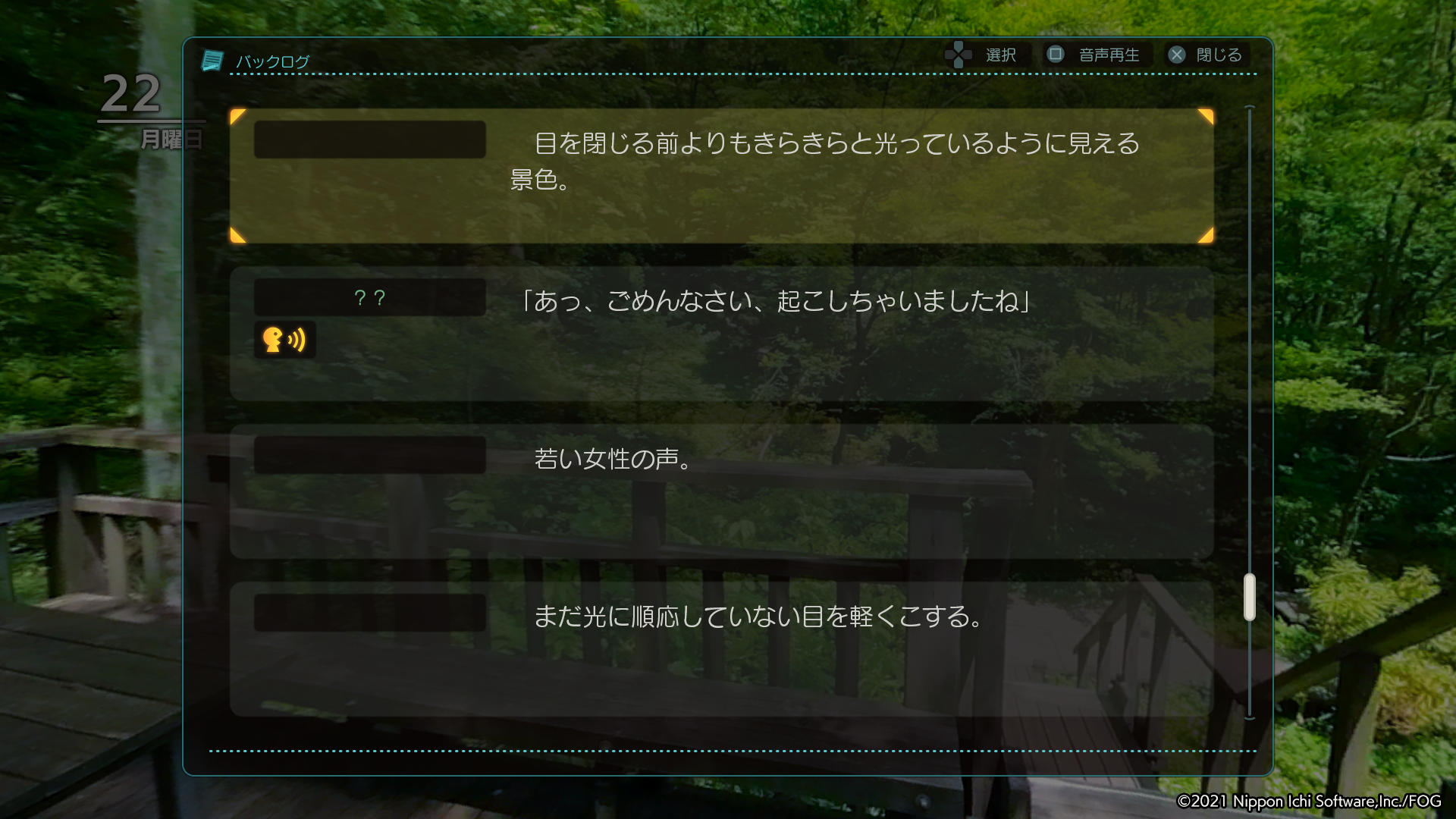
リリさんは、「腕に巻いたバンダナ」で主人公を見分けることができます。
では、バンダナこそがいちばん大事なのかというと当たり前ですがそうではない。
バンダナはあくまで見分けるための目印。
最近、「人を見分けること」以外の本質的なところでは、誰もがリリさんと同じなのかも知れないな、と思うようになりました。
目に見えるものは、情報を読み取るための目印。
綺麗な景色も、不思議な出会いも、珍しい出来事も、目で見て、頭に入ってきたとしても、それだけでは――
そこから何も読み取らず、何も感じなかったなら、見ていないのと変わらない。
そして、誰かにとっての見慣れた当たり前の風景が、他の誰かにとっては特別な最高の場所になることもある。
あるいは自分自身にとっても。
気分や知識、感情、心の動き次第で、見えるものは常に変わってしまう。
だから大事なのは、「目に見えるもの」の先にあるもの。
目で見たものの中から「見つけ」、「意識して」、「感じる」そのひとの「心の動き」なのだと思います。
・
・
・

「星の王子様」という有名な作品があります。
この作品の原題は「Le Petit Prince(直訳すると『小さな王子くん』)」で、「ある大人のため」に書かれた童話です。
童話なのに大人のため、というのも不思議なものですが、「大人は誰もがかつて子供であったから」と言う言葉が添えられています。
作者のサン=テグジュペリは1900年生まれ。
彼は、1903年(ライト兄弟の有人初飛行)以降の飛行機の発展と同時代を生きた、生粋の飛行機乗りでした。
12歳のときにはじめて飛行機に乗り、学校で文学を学んだあとは軍隊、民間、そして自分自身の飛行機を持って。
何度も何度も墜落し、大怪我し、軍を除隊されても国を変え、隊を変えてまた舞い戻り、44歳で命を失うるまで空を愛し続けたひとです。
彼が43歳のときに発表した「星の王子さま」という作品も、自家用飛行機で墜落し、砂漠の真ん中で遭難した際の自分自身の経験をモデルにしています。
今回はこの作品から一部引用しつつ、「自分にとって大切な存在」について、考えてみたいと思います。
「王子さま」は家一軒ぶんサイズの小さな星の住人。
話し相手もいない、たったひとりの王子さまでしたが、どこからか飛んできた種を大切に世話していたら、ある朝一本のバラの花が咲きました。
ある朝、ちょうど日の出と一緒に、その花は姿を現した。
そして、念入りにきちんと身じたくを終えたあと「なのに」、あくびをしながらこう
言った。
「うーん、私まだはっきり目が覚めていないみたい。ごめんなさいね、花びらがまだ整っていなくて…」
それでも、王子さまはすっかり見とれてしまって、思わずこう言った。
「ああ、なんてきれいな花なんだ!」
「うん、そうなの」
花は甘い声で答えた。
「太陽に祝福されて生まれたのよね、私 」
この花、性格はあまり控えめじゃないな、と王子さまはすぐに気づいた。
このバラが大変なツンデレで――本当に、漫画に出てくるような絵に描いたようなツンデレさんなので――、色々あってすれ違い、両者泣き別れのような形で離れることになり、王子さまは星を後にして旅に出ます。
「ぼくは何にもわかっていなかったんだ。
彼女が『言ったこと』じゃなくて、『してくれたこと』で判断すればよかった。
あの花は、いつもすばらしい香りと輝くような美しさでぼくを包んでくれていた。
ぼくは逃げたりしてはいけなかったんだよ。
あの花があれこれ困らすようなことを言ったのも、根っこではぼくを愛していたからだと気付かなくちゃいけなかったんだ。
花っていうのはとても気まぐれなもの。
だけどぼくは幼すぎて、あの花をどう愛したらいいのかわからなかったんだよ」
バラと遠く離れてから、色んな人と出会い、色んな経験を重ねて旅を続ける王子さまは、あるところで、一匹のキツネと出会います。
「こっちにきて、いっしょに遊ぼう」と王子さまがさそった。
「ぼく、今とってもせつないんだ」
「いっしょには遊べないよ。ぼくはキミと『apprivoiser』じゃないから」とキツネは答えました。
「あ、ごめん……」
王子さまはあやまったあと、じっくりかんがえて、こう答えた。
「『apprivoiser』って、どういうこと?」
apprivoiser
直訳すると飼い慣らす、なつかせる、馴染むというような意味になりますが、作中で語られる言葉の意味は、そのどれとも異なります。
apprivoiserは、「相互の関係性」をあらわす言葉だからです。
主従関係でも一方的な関係でもなく、意思を持った者同士がお互い相手を思い合い、心が繋がる対等な関係性。
心をゆるし合う、というのが近いでしょうか。
そんな「人と人、誰かと誰かの心の結びつき」を「星の王子さま」では、『apprivoiser』と表現しています。
「『apprivoiser』は『絆を結ぶ』ってことだよ。今ではみんな忘れてしまったけど」
キツネは答えた。「ぼくにしてみれば、今のキミはほかの男の子10万人と、なんのかわりもない。
キミがいなきゃダメだってこともない。
キミだって、ぼくがいなきゃダメだってことも、たぶんない。
キミにしてみれば、ぼくはほかのキツネ10万匹と、なんのかわりもない。
でも、キミとぼくが『apprivoiser』したら、私たちはお互い、相手にいてほしいって思うようになる。
キミは、ぼくにとって、世界でひとりだけになる。
ぼくも、キミにとって、世界でひとつだけになる」
『apprivoiser』とは、互いに必要と感じ、たったひとりの存在になること。
キツネは言う。
「ぼくの每日は、いつも同じことのくりかえし。
ぼくはニワトリを追いかけ、人間は私を追いかける。
ニワトリはどれもみんなおんなじだし、人間だってだれもかれもみんなおんなじに見える。
だからぼくは、ちょっとうんざりしてる。でも、キミがぼくと『apprivoiser』するなら、ぼくの每日は光があふれたみたいになる。
ぼくは、キミの足音を、ほかのどんなものとも聞き分けられるようになる。
ほかの音なら、ぼくは穴ぐらの中に隠れるけど、キミの音だったらすぐに穴ぐらから飛び出してく。それからほら、向こうに小麦畑、見えるでしょ?
ぼくはパンを食べないから、小麦ってどうでもいいものなんだ。
小麦畑を見ても、なんにも感じない。
それって、ちょっとせつないかも。でも、キミのかみの毛って黄金色でしょ。
だから、小麦畑は、すっごくいいものに変わるんだよ。
キミとぼくが『apprivoiser』したら、小麦は黄金色だから、見る度にぼくはキミのことを思いだす。
ぼくは小麦にかこまれて、風の音をよく聞くようになる」
『apprivoiser』のために必要なのは「時間」。
最初はちょっとだけ近くに座る。
互いの様子をうかがう。
言葉は誤解のもとだから、言葉ではなく態度で。
毎日少しづつ時間をかけて、意識して徐々にお互いの距離を近づけてゆく。
さらに、キツネは時間を守ることや日常のテンポの大切さを語ります。
「昨日と同じ時間に来てくれた方がいいよ。
たとえば、いつも午後の4時に来てくれるなら、3時からぼくは幸せになり始めるし、時間が経てば経つほど、幸せが増える。しまいには不安や心配になってくる。そうやって、幸せがかけがえのないたいせつなものだってわかるんだ。何事も『日常』が大事なんだ」
「日常って何?」
「『apprivoiser』と同じでみんなが忘れちゃってるけど、『日常』のおかげで、そうではない一日が別の日とは違う一日になる。ある一時間が、別の時間とは違う一時間になる。
もしみんなが思うがままに適当に暮らしたら、全ての日、全ての時間がみんな似てきてしまうから」
王子さまとキツネは『apprivoiser』して、つまり仲良くなってしばらく一緒に暮らすのだけど、王子さまはやっぱり自分の星に帰るための旅を続けなくてはいけないので、やがて別れの時がくる。
「はあ……涙がでちゃうな……」とキツネは言う。
王子さまは、
「ぼくはキミにつらい想いなんてさせたくなかった……
それでも、キミはぼくと『apprivoiser』したかったんでしょ」と言う。
「もちろん」
「でも、今にも泣きそうじゃないか。キミには何のいいこともなかったじゃないか!」
「いいことはあったよ。『小麦の色』だよ」
特別な存在とは、客観的には特別な存在ではない。
他の誰かにとってはありふれた、他と区別がつかないもの。
逆に、誰かにとっての特別も、自分にとっては他と見分けがつかない。
時間をかけて、心を傾けて。
その積み重ねによって、「自分だけのかけがえのない、世界でひとつの特別な存在」になっていく。
家族も、友人も、恋人も。
動物であれ植物であれ、自然物や人工物、使い慣れた道具、機械……
あるいは空想や創作物であってもだ。
それはふだん誰もが意識せず、当たり前にやっていること。
でもそのせいでときどき、その当たり前を見失ってしまう。
本当に大切なことは目に見えないのに、目で見ていることで満足してしまう。
「ものをよく見るためには、「自分の心」で見るんだ。本当に大切なことは目には見えないから」
別れに際して、キツネが自分なりの『秘密』を打ち明ける。
「キミがキミの大切なバラのためにかけた時間のおかげで――手間暇かけて、心を尽くして、注ぎ込んだ時間のおかげで、キミのバラはそんなにも大切なものになった。
そしてキミは永遠に、その関係に対して責任を持たなくてはいけないんだよ」「本当に大切なことは目に見えない。ぼくはぼくのバラに責任がある。永遠に」
王子さまはくりかえした。忘れないように。思い出せるように。
「さようなら」
「キミは永遠に、その関係に対して責任を持たなくてはいけない」
王子さまにそう諭す「キツネ」は、作者サン=テグジュペリの親友レオンウェルトがモデルであり、キツネとの会話で出てくる「バラ」は、「作者の妻であるコンスエロのことである」とされます。
王子さまとバラの関係は、作者と妻の結婚関係を描いたものでもあるのです。
空を愛し、世界を旅する、飛行機乗りの夫への不安や心配。
有名作家となったことで周囲の環境も人間関係もお互いの価値観も大きく変わっていって、夫婦で何度もすれ違い、別居し、離婚の危機に陥った夫婦関係。
それでも、大量に残されたラブレターや、作品内での描写から、心のつながりは切れることがなかったのでしょう。
「星の王子さま」刊行の一年後に、作者は偵察機での任務遂行中44歳で消息不明となり(近年になって撃墜されていたことが判明し)ましたが、「帰還後は妻のために、トゲのあるバラではなく、今度は星の王女様としての彼女の物語を描く」と約束していた、と言われます。
・
・
・
「キミだけが持っている星空」
キツネと別れ、バラを想いながら、旅の果てに王子さまは「僕」と出会います。
「僕」は飛行機乗りで、ある時エンジンの故障でサハラ砂漠に不時着したところでした。
傍からみれば「大人と子供の二人」は打ち解けて……
つまりapprivoiserして、たくさんのことを話し合いますが、一週間がたって、エンジンの故障は直らないまま飲み水がつき、ふたりは水を求めて砂漠を彷徨うことになります。
「砂漠が美しいのは、どこかに一つ井戸をかくしているからだよ ・・・」と、王子さま
が言った。
砂漠が不思議と綺麗に見える理由に突然思い至って、僕は驚いた。
僕は子どものころ、古い家に住んでいたのだが、その家のどこかに宝物が埋められているという言い伝えがあった。
もちろん誰もそれを見つける方法を知らないし、それを探そうとした人もいなかったのだろう。
でも、その宝物が家全体を魔法で包みこんでいた。
僕の家は、目には見えないその奥底に、秘密を一つかくしていたのだ ・・・
「そうだね」僕は王子さまに言った。
「家も、星も、砂漠も美しいのは、目に見えないものがあるからだね!」
「キミが、ぼくのキツネと同じことを言うなんてうれしいよ」
「こうして眠っている王子くんが僕をこんなにも感動させるのは、彼に花への変わらない想いがあるからだ。
眠っているときも、バラの姿が、ランプの炎のように王子くんの心の中で輝いているからなんだ ・・・」
なんでもないようなもの。
それまでなんとも思っていなかったものが特別なものになる、とはどういうことなのか。
誰かを、何かを大切に感じるとはどういう心の動きなのか。
王子さまは、自分の星から旅立ってちょうど一年の日に、星へ帰るため、この世でたったひとつだけのバラの元へ帰るためにある行動を起こします。
「大切なものは目には見えないんだ…」
「ああ、そうだね…」
「花と同じだよ。
もし君がどこかの星に咲いている一輪の花を愛していたら、夜空を眺めると甘い気持ちになるよ。どの星にも花が咲いているように見えるから…」
「ああ、そうだね…」
「だから、夜になったら星を見上げてね。
ぼくの星では、何もかもが小さすぎて、ぼくの星がどこにあるのか教えられないけど。
でも、きっとそのほうがいいんだよ。
ぼくの星は、君にとってたくさんある星のうちのどれかになるから。
そうしたら、君は『星空』を見るのが好きになるでしょ?
全部の星が君の友だちになるんだ。ぼくから君へのプレゼント」
そう言って、王子さまは声をたてて笑った。
「ああ、王子くん、僕は君の笑い声を聞くのが大好きだ!」
「人はみんな、星を持っている。でも人によって違うものなんだ。
旅をする人にとって、星はみちしるべになる。
そうじゃない人にはただの小さな光だ。
学者にとって星は研究するものだし、ぼくが出会った実業家にとって星は財産だった。
でも、どの星も、星自身は何も言わない。
君は、君にとっての、ほかの誰も持っていない星を手に入れることになるんだ」
「どういうことだい……?」
「どこかの星にぼくが住んでいる。
どこかの星でぼくは笑っている。
そう思えたら、夜に空を見上げると全部の星が笑っているように思える。
君は、君だけが、笑う星を手に入れることになるんだよ!」
そう言って、王子さまはまた声をたてて笑った。
「ぼくがいなくなっても、時がたって、悲しい気持ちがやわらいだらさ、キミはぼくと知り合ってよかったと思うよ。
キミはずっとぼくの友だちなんだ。
これからも、ぼくといっしょに笑いたくなるよ。
だから、ときどき窓を開けていっしょに笑って、楽しいって思ってね。
君が空を見上げて笑っているのを見たら、君の友だちは驚くだろう。
そしたら、こう言ってあげるといい。
『そうなんだよ、星はいつも僕を笑わせてくれるんだ!』
……みんな君の頭がおかしくなったと思うかな。
そしたら、ぼくは、君にひどいいたずらをしちゃったことになるね…」
王子さまと「別れ」て6年がたち、哀しみが少しずつ和らいで笑顔で星空を見上げられる様になった頃、「僕」はとんでもないことに気付いてしまいます。
「僕」は王子さまに頼まれて、ヒツジの絵を描いてあげたことがありました。
いつか星に帰ったとき、そこで飼うために。
それは、ふたりが仲良くなったきっかけでもありました。
でも、あのとき、ヒツジをつなぎとめるための、皮ひもを描くのを忘れていた。
これがどういうことになるのか。
「僕」は、つい、想像し続けてしまうことになります。
あのヒツジが、王子さまのたったひとつのバラの花を食べてしまったかもしれない。
いや、王子さまはきっと毎日バラに覆いをかぶせて守ってあげているに違いない。
そう考えれば満天の星空がまるで鈴を震わせたように輝いて感じるし――
でもうっかりして覆いを忘れたり、ヒツジが脱走して悪さをするかも…そしたらもう全部終わりだ…
そう考えてしまえば、満天の星は涙の音を流す。
ここには大いなる神秘がある。
王子さまのことが大好きなキミたちにとっても、僕にとっても、どこか知らないところで見たこともないヒツジが1輪のバラを食べてしまったかどうかで、世界のすべてが変わってしまうのだから ・・・
空を見上げてごらん。
そして「ヒツジはあの花を食べてしまったのか、それとも食べていないのか?」と、自分にたずねてごらん。すると、すべてがどれほど変わってしまうかわかるだろう ・・・
でも、大人たちは誰も、これがどれほど大切なことなのか、けっしてわからないだ
ろう!
これは僕にとって、この世でもっとも美しく、もっとも悲しい景色だ。
・
・
・
「ぼくの、星空」
きっと、自分がこのブログを書き続けているのも、そういうことなんだな、と思います。

彼と彼女、ふたりの旅が今日も明日も続いていくと。
自分にとっての特別な星空を、いつまでも、自分の心の中で輝かせ続けたいから。


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.
「キミがキミのバラの為に費やした時間こそが、キミにとってのバラを、かけがえの無いものにしているってことだよ」





コメント