リリと出会った岐阜の夏から暦は巡り、島根には春が訪れている。
今、俺達が腰掛ける縁側には、「食べて!」と言わんばかりに甘く濃密な香りを漂わせているりんごが小さな山を作っていた。
お店によく売られているふじや王林よりも二回りほど小さく、形も歪み、すり傷だって多い。はっきり言って、ぶかっこうな見てくれだ。
しかし、春のぽかぽか陽気の下、真っ白な雪をまとってきらきらと輝くりんご達は、俺の心を心地よく震わせてくれる。
季節の流れが圧縮されたような、その邂逅を写し撮りたくなって、カメラのシャッターを切った。
隣に座るリリを見ると、手に持っていた果実に神妙な顔つきでかじりついて、
「…………うん!」
パァッと笑顔になった。
あとに言葉を続けることもなく、いたく幸せそうに、食べることに集中している。
いつものことながら本当に美味しそうに食べるものだと感心しつつ、俺も、りんごの山に手を伸ばした。
このりんごは、数ヶ月前の俺達からの贈り物だ。

・この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
・風雨来記4「母里ちありとのその後」を
題材にした二次小説・ファンアートイラストです。
・当サイト内に掲載している二次創作物について不都合等がありましたら、
ページ上部の問い合わせ欄よりご連絡ください。
雪の下のタイムカプセル
<前編>
主な登場人物
キミ:東京から島根の母里家へ婿入りした、フリーのルポライター
リリ:本名は母里ちあり。21歳
【農業とルポルタージュ】
りんごについて語るためには、まず俺達の近況について触れなくてはならない。
4月に入って、畑に残っていた冬野菜はあらかた片付き、春の収穫も今後の作物への準備も一区切り。田植えにはまだ少し早い。
こういう作物の合間の時期を、端境(はざかい)と言う。
端境が生まれないようにあれこれ工夫をしても、結局は自然が相手だ、そうそう思うようにはいかない。
母里家の家業も今、春の端境期にある。
一方、俺自身の「家業」……晴れてフリーでの活動を始めたルポライターの仕事の方はというと、ありがたいことにこちらは端境ということもなく。
古巣である「ぐるり」からの依頼だけでなく、のひコンでの記事や、独立を期に開設したウェブページやSNSを通じでのオファー。松江の出版社からは、「都会からの地方移住」をテーマにした短期連載の打診も来ていた。
まだまだご祝儀的な側面も大きいだろうから油断はできないが、滑り出しと言っては順調といっていいだろう。
夏に向けて、俺自身がたてた旅の企画も動いている。
これはまだまだどう転ぶか分からないけれど、将来的には一番力を入れたいところだ。
俺は、フリーになるにあたってひとつ、意にそぐわない仕事……自分の『旅』からかけ離れた依頼は、どれだけ条件が良くても受けないと言う方針を定めていた。
ぐるり編集部に在籍していた頃に感じた迷いと同じ轍を踏まないように。
『好きなことを仕事にできるって幸せだね』
岐阜で出会った頃、リリは何度かそう言ってくれたが、あの時の俺は素直にその言葉を受け止めることができなかった。
好きだからこそ色々迷ったり、悩みを抱えることもある、と。
求められることと、できることのすり合わせ。
仕事をする、とりわけ、会社組織で仕事をするというのはそういうことだ。
確かに、俺の場合は上司である渋川デスクの理解もあって、「求められること」に自分の「やりたいこと」をかなりの部分で重ね合わせることができていた。
その意味では、リリの言う通り幸運だったのは確かだ。
ひとつひとつの仕事で見れば、何か決定的に大きなずれがあったなんてことも無かった。
それでも、小さな不満や違和感が何年もかけて積もり積もっていくうちに、自分の立場に、窮屈さを募らせていく結果になった。
それは誰が悪いというよりも、根本的に俺の性分が会社勤めと相性が悪かったのだろう。
そんなときにずっと道標にしていた、「あの人」のサイトを見失った。
これがさらなる追い打ちとなって、自分の将来についてずいぶん迷っていたのが岐阜の旅の頃だ。

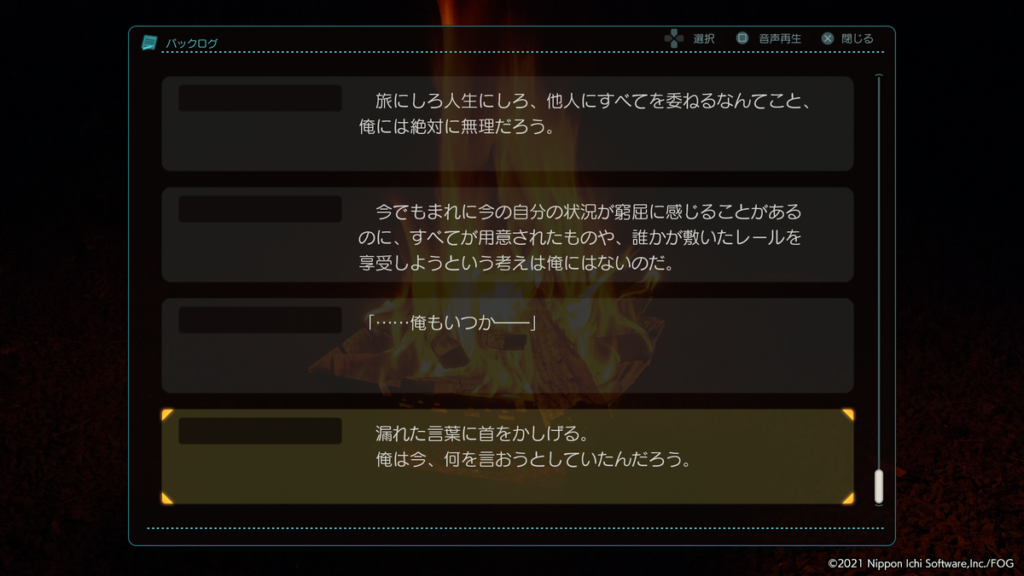


リリとの出会いがきっかけで、こうしてフリールポライターとしての道を歩み始めた。
独立して間もない今、「生活のための仕事」という考え方であれば、軌道に乗るまで、多少理念からずれた内容や条件でもとにかく受けて、数をこなすべきという意見も当然あるだろう。
だが、ありがたいことに俺の場合は、母里の家に婿入りしたことで安定した生活の基盤を得た。
リリとの夫婦生活。
農業という仕事。
旅から旅へと一年の大半を旅の中に生きる、風来坊な生き方をする未来は失ったが、その代わりに、俺が選び得た、もうひとつの自由。
それは、生きるため、収入を得るために、ではなく、自分自身の琴線、興味のアンテナに触れた仕事――旅を選ぶことができる自由だった。
渋川編集長は、俺がMG書房を去るとき、こんな言葉をかけてくれた。
『生活の柱がすでにある以上、ルポに関しては、自分の目指す道に繋がる仕事だけを選べよ。
これからの時代をフリーでやっていくなら、自分自身をブランドとしてどう作り、どう見せていくかが重要だってことはお前さんも分かっているだろう。
依頼相手の実績を、だれでもネットで簡単にたどれる世の中だ。
仮に、こだわりなく片っ端からたくさん依頼をこなせば、信用や筆の速さをアピールできる。
それももちろん立派なブランドだが、お前がこれからやりたいのはそういうことじゃないんだろう?
選り好みというと言葉は悪いが、選んで積み重ねた仕事の実績それ自体が、お前というブランドを作っていくんだ』
『はい。ありがとうございます。……しかしそうすると、ぐるりからの依頼であっても断る可能性がありますね』
『お、おう』
『是非俺が受けたくなる仕事をお願いします』
『こいつ、誰かさんに似てきたな。言うようになった。いや、いい。それくらいの気概でいけ。島根に行っても頑張れよ』
選択と言えば……
つい先日も、地元のとあるウェブメディアからメールで打診があったのだが、自分には不向きだと判断して断るつもりでいた。
なにせ、
「仲良しカップルの週末デート・二人だけの神話体験☆縁結び風土記の旅」
とかいう企画テーマだ。
意にそぐわないという以前に、俺よりも適任がいくらでもいるだろう。
どうも「新婚のフリールポライターだから」という理由で俺に白羽の矢をたてたらしい…。
担当者からは是非に、とやたら熱意のこもった長文のメールが送られてきており、無碍にするのは少々心苦しくもあるのだが、俺のルポ、旅のスタイルと、カップル向けの旅行プランというテーマは、ミスマッチとしか思えない。
少なくとも、ぐるり時代の俺には決して回ってこなかった仕事で、それは今も……
ミスマッチ……だよな?
微妙な引っかかりがあって、即、断りのメールを返さなかったのは、リリの影響が大きい。
『キミは女の子にセクシーな写真を頼むのは恥ずかしいって言う自分の殻を破ったんだよ』
『普段なら選ばない道も、あえて選んでみようって思えたよ』
一時は俺に仕事を辞める覚悟までさせたのもリリならば、今もこうして最高の一枚という夢を追いかけている俺がいるのもまた、リリのおかげだ。
母里の両親が俺の「複業」に理解があるのだって、結婚前からリリが何度も何度も説明、説得してくれていたからだということを、最近になってお義母さんからこっそり教えて貰った。
相も変わらずあきれるような冗談を言ったり、たまに年下の弟にするみたいにからかってくるのは勘弁してほしいけど、それ以上に、リリには色々なところで支えられているな、と感じることが最近の常だった。
きっと、未だ俺の気付かないところでも、さりげなく色々と尽力してくれているのだろう。
…………普段なら選ばない道か……
【神話の母里】
ともあれ、農業は端境、ルポの方も今週はお休み。
降って湧いたようなこの休暇を、日頃からの感謝を込めて奥様への家族サービスに勤しむことにしたのだった。
お義母さんが『たまには二人で出かけたら』、と快く送り出してくれたこともあり、ここ数日はリリと連れだって、斐伊川の桜並木へ花見ツーリングしたり、街で買い物に付き合ったり、日帰りで県内の秘湯を巡ったり、リリのお気に入りカフェで時間を忘れて他愛もないおしゃべりをしたり、宍道湖に夕日とうさぎを見に行ったりと、ある意味で普段以上にめまぐるしい時間を、二人で楽しく過ごしていた。
そんなこんなで、今朝のこと。
以前、春の山菜に興味があると、俺が何気なく話したことを覚えてくれていたのだろう。
リリに誘われて、家の裏山で山菜採りをすることになった。
このあたり一帯の山は、母里家に代々伝わる私有地――いわゆる持ち山だ。
持ち山自体はこうした山間部の土地では珍しくはないが、最近仲良くなった近所のおばあちゃんによれば、母里の山の起源は、遠く出雲国風土記の時代にまでさかのぼるのだという。
にわかには信じがたい。
なんでも、出雲の主神であるオオナモチが天の神の勢力に国譲りをする際にここへやってきて、「この土地だけは、青く木の茂った山を垣のように巡らせて、自分自らが玉のように愛で『守り』続けよう」と言ったこと。
また、かつて多くの神々の『母』であるイザナミがこの地で暮らしていたとされること、などが「母里」の名の由来なんだとか。
確かに周囲が山に囲まれた土地ではあるが……
一度、こうした伝承についてリリにどう思ってるのか聞いてみたときには、
「うーん……昔話のことはよく分からないけど、子供の頃から山で遊んでると、金属の破片とか珍しい貝殻とか、たまに拾ったよ」
といって、押し入れの中から子供の字で『たからもの。』とでかでか書かれたクッキー缶を大事そうに引っ張り出して、見せてくれたものだ。
中には青く錆びた銅らしき金属片や、ヒスイらしい薄緑色の小石、何か図形のようなものがかかれた土器の破片などが整理されて収められていた。
「この貝とかさ、コメカミって言う名前らしいんだけど。兄さんが調べたところでは、古代のお金か、安産のお守りだったんじゃないかって」
そう言って親指と中指でつまみあげたのは、たまご型の貝殻。
タカラガイの一種だろうか。
貨幣の貨という字に貝が入っているのは、漢字が生まれた古代中国でこの種の貝が、通貨として用いていたからだ。
「貿」易、「貴」重、「賣買」、「財」産、品「質」、「費」用……など、金銭や価値に関係のある文字の多くには「貝」が含まれている。
宝という字も、元々は寶と書き、貝をあらわした文字だ。
有名な竹取物語に出てくる、かぐや姫が結婚の条件として提示した宝物のひとつもこの貝だとか。
タカラガイ自体は一部の種を除けば、現代においては特段珍しいものではない。
俺が以前旅した四国でも、太平洋側の浜辺を歩けば貝殻を見つけることがあった。
沖縄では、お土産物屋さんで安く売られている程に身近な存在だとも聞く。
とはいえ、南洋のものが島根の、神話伝説の残る山中で見つかった、とくれば「もしかして大発見なんじゃないか?」とも考えてしまうけど……どうなんだろうな。
結局、素人の俺達の目ではその「コメカミ」を含め、リリの「たからもの。」の考古学的価値がいかなるものかはよく分からなかったので、そのうち専門家に鑑定してもらおうということになっている。
【山の幸】

朝食もそこそこに家を出て、青々と新緑が生い茂る裏山を目指した。
前を歩くリリは、いつもより丈の長い、足首を隠す長めのデニムパンツに長袖のシャツ、スニーカーという服装で、右手には園芸用の小さなハサミをひとつ持っている。
俺も似たようなもので、軍手をつけた手にはハサミではなくビニール袋が数枚。首からはカメラを提げていた。
「山菜採りって、こんな軽装備で大丈夫なの?」
「今日行くとこなら十分十分」
「ナタとか要らないの?」
「藪漕ぎするわけじゃなし、山菜採りにそんなの使わないって。あ、じゃあ、これ持ってくといいよ」
そう言って、畑の隅の用具入れから短刀のようなものを引っ張り出して、俺に渡した。
長さ30センチほど。シルエットだけ見るとまるで神話に出てくる剣みたいだ。
「これは何?」
「何って……スコップだけど」
「へえ。面白い形だね」
「切ったり削ったりもできるし、けっこう便利だよ」
「へえ」
「それじゃあ、いこ!
熊避けに、なるべくおしゃべりしようね」
「……」
リリの案内で、まず畑に残っていた収穫時期の過ぎた小松菜や白菜から生えた菜花を摘むところからはじめて、田んぼのあぜではツクシや田ぜり、ノビルを採った。
木陰では、ノカンゾウの若芽にハルシメジ、驚く程大きなミツバ、ヨモギの若葉。
山裾に至れば、つぼみの開いたふきのとうやワラビ、ぜんまい、緑の香りの強い山ウドやコゴミ。
沢辺では白い小花をたたえたクレソンやわさびの葉、ウワバミソウ。
「あと何週間かしたら、採れる種類がもっと増えるよ」
と良いながら前を歩くリリは、俺には道ばたの草にしか見えないものを摘み取っては「ウルイ。サラダかおひたしにしよう」、頭上を見上げては「あ、タラの芽もう出てるね」と名前や簡単な食べ方を解説してくれる。
そんな様子を逐一メモして、カメラに収めていく。
ミョウガダケ、イタドリ、あけびの新芽、葉山椒、ハナイカダ、オニヒカゲワラビ……
収穫は順調に増えていく。
ウコギ、オドリコソウ、ヤマツバキ、ユキノシタ、モリアザミ、シオデ、コシアブラ、タカノツメ……
……増えすぎて、もはや何がなにやら把握しきれなくなってきた。
メモ帳は、半ば暗号表と化しつつある。
これは俺一人で来ても、猫に小判だな……と感心することしきりだ。
春の野山は、俺にはまだまだ見分けられない宝の山に満ちている。
【夫婦の距離】
「見分ける」と言えば、リリの個性……相貌失認について、あれからも色々と調べてきた。
リリの見ている景色や悩みを、もっと理解したい……彼女の目線に少しでも寄り添いたいと思ったからだ。
顔を見分けるという行為には、脳の側面にある、「紡錘状回顔領域」という小さな部位の働きが関係していると言われている。
実際の顔に限らず、漫画のデフォルメキャラクターの顔、動物の顔、はたまた(^_^)のような文字の集合であっても、『顔』だ、と認識できるのはこの器官の働きによるもので、生まれた時にはすでに基本的な能力は備わっているそうだ。
ただし、最初はあくまでも、「顔」を認識するだけであって、「個人」を識別する能力に関しては生まれた後の経験によって培われ、獲得していくものだと考えられている。
子供の「人見知り」や、人種の違う人だと見慣れるまではうまく見分けられない問題も、そこに理由があるのかもしれない。
相貌失認を持つ人の場合は、この識別の「経験」をうまく積み重ねることができないそうだ。
軽度のものも含めればこの症状を持つ人の割合は、人類のうちの1%とも、2%とも、もしかしたら一割にものぼるかもしれないと言う説もあるらしい。
数字がはっきりとしないのは、リリもそうだったように、顔が覚えられなくてもそれ以外の情報で総合的に判断して見分けたり、見分けられなくても問題にならないような振る舞い方を身につけていったりと、自分の中だけに問題を抱えて、工夫しながらうまく生活している場合がほとんどだからだそうだ。
「見分けられないというそういう個性」
リリの親友、月子さんは小学生の時に、そんな風に言ったという。
今のように、明るくてポジティブなリリに変わったきっかけの言葉。
雪花月子こと橘月子さん。
彼女とはあれ以降リリを介して何度か会話を交わした程度だが、未だに謎だらけの人だった。
そんな月子さんによれば、相貌失認に関して、後天的に症状を持った場合の治癒例はあるそうだが、先天的な場合はまだはっきりした治療法は見つかっていないということだ。
それでも、幸福感に関するホルモンが関係することが分かってきていたり、相貌失認向けの識別トレーニングなども海外では研究・開発されているそうなので、将来的に状況が変わることだってあるかもしれないとも言っていた。
月子さんは幼い頃から今に至るまでずっと、リリを案じ、その苦労に寄り添っているのだ。
そんな一番の理解者である月子さんでさえも、いるはずのない場所で鉢合わせしたとき、リリは全く気付くことができなかった。
岐阜――付知峡での、不意の再会だ。
あの時のことは、リリには伝えないでおこうと月子さんと決めていた。
それをわざわざ教えたところで、リリをいたずらに傷つけるだけだろう。
そしてそれは月子さんだけじゃない。俺だって立場は同じだ。
リリは、俺の顔を未だに覚えてはいない。
ある程度近くにいれば、言葉を発しなくても息づかいとか匂いを含めた『雰囲気』で分かるようだが、それが届かない距離まで離れたときは、未だに「腕のバンダナ」が俺たちの道標だ。
おそらく、この先もそうだろう。
だが、そんな現状について、俺も、リリも、最近はおおむねポジティブにとらえている。
俺を見分けようといつも一所懸命になってくれる彼女を見るたび愛おしく思うし、俺も少しでも彼女が見分けやすいように、顔で分からないなら全身で伝えようと、一所懸命になる。
そしてそれはお互いさまだ。
他の部分で……たとえば今こうやって山を歩いているときや、街のちょっとおしゃれなお店へ出かけたときのように、立場が逆になることもしばしばで。
自分が知らなくて彼女が知っていることを、俺は積極的に知ろうとするし、リリも親身に教えてくれようとする。
お互いを尊重する気持ち……と言うと大げさかもしれないが、世の中の見え方が違うという、夫婦であっても決して分かち合えない問題が俺達の間にあることがかえって、その距離を少しでも埋め続けるため、様々な形で相手に向き合う努力につながっているように思う。
案外それが、俺達が大したすれ違いもなく、楽しく夫婦生活を送れている秘訣なのかもしれない。
最近、そんな風に思う。
【とある竹の旅路】
山へ入って半刻もたたず、持ってきた3枚のビニール袋が、山菜でもれなくぱんぱんに膨らんでいた。
数日はおかずに困らなそうだな。
そろそろ帰ろうかと話していたところで、眼前ににこんもりした竹林が見えてきた。
先日、お義父さんの知り合いの竹林でタケノコ掘りを体験したばかりだから、ついつい地面を見渡してしまう。
「あれ。ここの竹林にはまだタケノコ出てないんだな」
「これはマダケだから、採れるのは梅雨の頃だね」
「へぇ。ふだんよく見かけるタケノコの竹とは種類が違うんだ?」
「よく見るのは孟宗竹って言って、春のたけのこ。
江戸時代に日本に持ち込まれて、大人気になったんだって。
ここのはマダケって言って、かぐや姫にも出てくるむかし話の竹」
なるほど。『竹』と一口に言うけど色々種類があるのか。
「詳しいね」
土地や人の固有名詞覚えるのは苦手だけど、動物のこととか興味を持って覚えたことを、こんな風にわかりやすく説明するのがリリはとてもうまい。
「小さい頃、山とか田んぼで遊んだあとに兄さんと一緒に図鑑や百科辞典を開いて、見つけた草花とか、いきものの名前とか生態を調べるの、好きだったんだ」
なるほど。自然を学ぶには最高の環境だな。
リリの動物好きのルーツも、きっとそこにあるのだろう。
「マダケって、120歳で寿命を迎えるんだよ」
「え、寿命が決まってるの?」
「うん。そうなんだって。120歳になると日本中のマダケがほとんど同じタイミングで一斉に花を咲かせて、種を飛ばして、枯れちゃって。それで新しく芽吹いて、また120年生きるんだって」
「不思議だな……120年で一斉にっていうのは、何か理由あるのかな」
「うん、あるみたい。えっと、キミは、クローン技術って知ってるかな」
「同じ遺伝子を持ってる別々の個体……みたいな意味だよね。クローン羊とか、クローン牛とか」
「それそれ。さすがルポライター。
植物だと、クローンって昔から珍しくないみたい。
クローンって言葉自体が元々『小枝』って言う意味で、ほら、接ぎ木ってあるでしょ」
接ぎ木とは、ある木の枝を、相性の良い別の種類の木の特定の部分にキズをつけてそこに差し込んで固定することで、融合してひとつの植物として育っていく習性を利用した技術のことだ。
一本しかない、種の無い突然変異の木や、種からだと大きく育つまでに枯れやすい植物を効率的に増やす方法。
枝から増やしすので、当然ことながら、すべて同じ遺伝子=クローンになる。
「確か、みかんとか、ソメイヨシノは、そうやって増やしていると聞いたことがあるな」
「それそれ」
リリがうなずいた。
「で、マダケの話に戻るんだけどね。
竹って、竹林全部が、根っこでつながってるおっきなひとつの生き物なんだよね」
「えっ、そうなの?!」
周りを見回してみる。
この、視界全部を埋め尽くす竹林全部が、縦横無尽に伸びる根で繋がったひとつの生物。
そう考えると、まるで、神話に登場する多頭の蛇神、ヤマタノオロチのようにも見えてくる。
「でもね。ひとつの竹林だけじゃなくて、日本中のマダケも、不思議なことに全部遺伝子が同じなんだって」
「え、ソメイヨシノみたいにってこと?」
「そう。ソメイヨシノみたいにってこと。
だから、120年の寿命の周期が一緒なんだって」
「自然界で、そんなことあるの?」
「うーん……絶対にない、というわけじゃないだろうけど、誰かが他の土地から持ち込まんだひとつのマダケが全国に広がったもの、って考える方が自然なのかもしれないね」
途中途中記憶を辿るように、ゆっくりとリリが解説してくれた。
そこまで話すと、少し微笑んで。
「この先、私とキミとの間に赤ちゃんができたときには、その子はキミの遺伝子と私の遺伝子をはんぶんずつ持って生まれてくることになるでしょ」
「……」
「でも、日本のマダケの場合は、みんなが同じ遺伝子を持っているから、その花同士が受粉して生まれる次の子供も、やっぱり同じ遺伝子のまま……それを、千年か、二千年か、もっと長いこと、続けて来たのかもしれないねぇ」
「……」
「あれ…………どしたのキミ?
なんか口元がゆるんでない?」
「いや、別に」
「? ……へんなの。私、何かへんなこと言ったっけ」
「いやいや、別に」
リリは、少し考えた後、「ああ」と手をぽんと打った。
このジェスチャーも、実際にやる人滅多にいないぞ。
「なるほどなるほど。そういうことね」
「え、な、何だよ」
「ふふ。キミのそういうとこ、ほんと可愛いよね」
「な、何がだよ」
「幸せな未来を想像しちゃってましたーって、素直に顔に出ちゃうとこ」
「……」
く、雲行きがあやしくなってきたぞ。
「でもさ、前に私が『そろそろ欲しいね』って言ったとき、『リリに今しかできない、やりたいことが見つかるかもしれないから、もう少し待とう』って先延ばしにしたのはキミで、そうでなかったら今頃私達の……」
「そ、それにしてもちあり先生、さすがですね。マダケの解説、感服しましたよ、ちあり先生。やっぱり山のことならちあり先生だな。かっこいいですよ、ちあり先生は」
「う、ぇっ?! もー、こらぁっ!」
リリが顔をしかめて話を止めた。
先生呼びされると、相変わらずくすぐったくて照れてしまうらしい。
苦肉の策で話を変える作戦は功を奏したようだ。
「いい度胸だね、キミ……。
これはあらためて、しーーーっかり夫婦で話合わないと」
やばい免罪符を渡してしまったかもしれない。
あわててさらに話を変える。
「そういえば、ほ、北海道でクマザサっていうのをよく見たんだけどさ」
「あっ、誤魔化した!」
「た、竹と笹って違うものなのかな?」
「……んー。微妙?
『大根とカブ』くらいには違ういきものだと思うよ」
「なるほど、属が違うのか」
おおざっぱに言えば、「属」は、交雑……つまり雑種ができるかできないかの分類だ。
「属」が違うなら基本的には交雑しないし、してもその次の子孫につながらない。
たとえば、大根とカブは同じアブラナ科で見た目も似ているけれど、大根はダイコン属、カブはアブラナ属なので、雑種は生まれないわけだ。
しかし、ブロッコリーやキャベツ、小松菜などはアブラナ属なので、カブと一緒に育てると、容易にそれらが入り交じった雑種……別の野菜が生まれる。
これを人為的・選択的に行うのがいわゆる「品種改良」だ。
交雑自体には、本来良いも悪いもない。
だが、母里家では江戸時代以前から伝わる「在来種」を何種類か守り続けて来ていて、これが他の野菜と交雑してしまうと文字通り、種の……すなわち伝統の根絶に繋がってしまう。
そのため、在来種の畑だけは、交雑の危険のある花粉が飛んでこない離れた場所に作ったりと、手間や苦労が多い。
こうした固定種の保存については、農業を手伝うようになって最初の頃に、お義父さんから厳しく叩き込まれたところだった。
「あー……、でもでも。タケとササの違い、実際はもうちょっとアバウトかもしれないよ」
「というと?」
「この山の上の方に、マダケとササの雑種があるんだ」
「え……、普通は雑種が生まれない組み合わせだろ?」
「そうだね、普通は」
「じゃあ、それって、めちゃくちゃ貴重なんじゃないか?」
「うん、かなり珍しいと思う。島根県内にもう一カ所生えてるところがあって、そこは確か、県の天然記念物になってるよ」
属が違う生物同士の人為的な雑種が生み出された例は、少なくない。
たとえば、ウマとロバの雑種はラバと呼ばれて、両親の良いところを併せ持った賢く頑丈で優れた家畜として、紀元前のエジプトから重宝されていたそうだ。
近年でもトラとライオンの雑種だとか、りんごとなしのハーフだとか、観賞用のカトレアとか、色々な実験・研究がされている。
が、それらもあくまでも人為的なものであり、ごく一部の例外を除けば、『属間雑種は繁殖能力を持たない』というのが通説だ。
「日本中のマダケは全部クローン、同じ個体って話だったよな」
「うん」
「そうすると、その雑種だけは別の存在になったってことかな。マダケとササの遺伝子を持った、そこにしかない、新しい、別の種に」
「あ、そうかも。それ、けっこう面白い着眼点だと思う」
遠い別の場所からひとりで旅をしてきて、ありえないと思っていたはずの相手と巡り会って、ありえないと思っていたはずの道を選んで、その土地に根付いて、それまで想像もしていなかった生き方をしている。
『キミがありえないって言った展開、私がキミに見せてあげるよ』
なんだか、自分のことに、重ねて考えてしまう。
「是非一度見てみたいな」
「山の上の方は獣道になるから、今日の装備だとちょっと不安だね。今度また来よっか」
「そうだね」
竹と笹の雑種……と、メモにつけておく。
「その頃には、ヒメタケもとれるよ」
「ヒメタケ?」
「そう。大きめの指くらいのサイズの、可愛いタケノコでね。キミのさっき言ったクマザサの新芽だよ」
「へえ! ……でも、クマザサの子なら、タケノコじゃなくてササノコなんじゃ?」
「ふふ、そうだね。ササノコだね」
クマザサは、北海道では至る所でよく見かけた、俺にとってはなじみ深い植物だ。
健康に役立つ成分があるとかで、「熊笹茶」なるお土産になっていたのを見たし、「クマザサソフト」というご当地スイーツを食したこともある。
たくましく、雑草のようにうっそうと生えているイメージがあったから、芽生えを想像したことはなかったけど、なるほど、あれも元々はタケノコ的な姿で生まれてくるわけだ。
いつか、次に北海道に行く機会があったときには、地面にも気を配ってみよう。
【誰でもない、キミだけの道】
竹林を背にして、帰路につく。
他愛もないおしゃべりをしながら、ふと思いついたことがあった。
「なあリリ」
「ん?どしたの」
「こんな山の中にああやってぽつんと竹林があるってことは、むかし、誰かがこのあたりにまで根だか種だかを運んだってことなのかもしれないな。たとえばそれこそ、風土記の時代とかにさ」
「なるほど。そう言うこともあるかもしれないね」
「とすると、あの竹林も、古代の交流の証であり、旅人だったってことだ」
「ほー。……うんうん、キミらしい視点だね」
リリは少し目を細めた。
「古代の交流の証かぁ。ふふ、垂ちゃんが聞いたら、テンション上がって飛んできそう」
彼女の友人に、こう言った伝承や民話に関する専門家がいて、その人物の名が「垂ちゃん」と言う。
本名は、鵜瀬垂(うのせしづる)さんといって、名古屋の大学院で伝承について研究している女性だ。
美人で落ち着いた外見と、好きなことには一直線!で、好奇心旺盛な男の子のような中身とのギャップが面白い女性だった。
リリとは、あの岐阜の旅の中で知り合ったという。
鵜瀬さんは鹿児島の田舎育ちということで、同じく田舎育ちのリリと通じ合うものがあったらしく、以来親交を続けているようだ。
そんな鵜瀬さんだが、以前一度、免許取得したばかりだと言うバイクに乗って、はるばる島根までツーリングに来たことがある。
これが人の縁の面白いところで、その時一緒にやってきた彼女の恋人という男性――彼もまたルポライターをやっており、俺と同じく「のひコン」にも参加していたらしい。
バイク乗りで、北海道が好きで、極めつけに、今の仕事についたきっかけが俺と同じ「あの人」のサイトに感銘を受けたからだと言う。
それを聞いたときは、え、この人俺じゃないか!と思わずツッコんでしまった。
向こうもきっと、同じように思ったことだろう。
世の中には自分とそっくりな人間が3人はいる、なんて話を聞いたこともあるが、彼とは他人とは思えないシンパシーを感じてしまった。
男二人が口を揃えてそんなことを言うと、リリも鵜瀬さんも、俺と彼を見比べて「全然似てないよ」と笑っていたっけ。
リリの場合は顔では見分けられないから、そもそも雰囲気が違う、と言うことだろう。
また、鵜瀬さんが言うには、「母里さん(この場合は俺のことだ)の方がだいぶ落ち着いている」らしい。彼は少々不本意な顔をしていたが、後々リリ経由で聞いたところによれば、つまるところ単なるのろけだった。
今の鵜瀬さんからは想像もできないが、彼と出会う前までの彼女は、自分を何重もの殻に閉じ込め、抑え込みながら生活していたらしい。
そんな彼女を今のように変えたのが彼で、鵜瀬さんの笑顔を見るためにしょっちゅう冗談を言ったり、あえて感情をあらわにしたり、色々なところへ連れて行ったりと、ずいぶん骨を折ってくれたのだそうだ。
ボクを笑わせるためにしょっちゅうバカなこと言ったりやったりするので困ってるんだ、と言葉とは裏腹にうれしそうに、鵜瀬さんは語っていたのだという。
実際、彼と深く話してみるほどに、通じるところも多かったものの、それ以上に、お互いの興味の向いている方向が随分違っていたのが印象的だった。
彼は、伝承研究者である鵜瀬さんの影響を受けてか、ルポルタージュを、「人から人へと時代を超えて伝わっていく、情報のスタート地点」だと捉えているらしかった。
書いて、読まれて、知られて、それで終わりではない。
それが、伝えた人の「心を打てば」、その人もまた誰かに、その感動を伝えるかもしれない。
そうして読み手や伝え手を経る毎に少しずつ変化していく。形を変えながら生き続けていく。
まさに「伝承」だ。
ルポの仕事をそういう風に捉えたことがなかったので、とても刺激的な発想だった。
向こうは向こうで、俺について、惚れた相手と一緒になるために会社を辞めて独立する情熱と行動力がすごい、とやけに感心していた。
お互い、出会った相手によって、多大に影響を受けたのは間違いない。
当たり前だが、たとえ、何かを始めるきっかけが同じだったり、元々の価値観が似ていたとしても、人生の旅路……出会った人や通った道、自分だけの経験の積み重ねによって、人は変わっていく。
俺自身、リリと出会う前の自分と、出会ってからの自分の変わりように日々驚いているのだから。
二人とも、元気にしているだろうか。
次の夏が来たらあらためて島根に遊びに来ると言っていたな。
またゆっくりと、話してみたいものだ。
【幕間】
来た道を戻りながら他愛もない話を交わす。
手に提げた袋に満載の山菜がずっしりと重い。
「大漁大漁ー。今日からの食卓は山菜三昧だねぇ」
リリが軍手の甲で額の汗をぬぐいながら笑う。
「リリのおかげだよ。ありがとう」
「どういたしまして、旦那さま。手料理、期待してるから」
「ああ。それにしても、秋はアケビとか山栗とか木の実が多かったけど、春は地面や木の枝から生えてくる草とか新芽とかが多いんだね」
「そうだね。春ってやっぱり、暖かくなって、雪が解けて、新しい命が芽吹く季節だから……」
機嫌良く相づちを打っていたリリが、ふと立ち止まった。
「リリさん?どしたの」
「私、今なんて言ったっけ?」
「え? 新しい命が芽吹く季節って」
「んー……?その前は?」
「えーと……春って、暖かいから、雪が解けて……?」
「雪…………? 雪が解ける………… あーっ!!雪だ!」
リリは唐突に大声をあげて、俺に飛びついてきた。
「な、なんだなんだ?! どうした?」
「タイムカプセルだよ、タイムカプセル!」
「は?たいむかぷせる?」
突然飛び出てきた謎のワードに、おそらく俺の目は点になっていたと思う。
いきなり何を言い出すんだうちの奥さんは。
「ほら、埋めたじゃん、一緒に!」
「ええっ?」
「だから、ほら、雪だよ、雪! 雪の下!」
「雪の下………………ああ、あれか!!」
ようやく思い至った。
どうして忘れていたんだろう。
「行こう!」
「うんっ!」
二人して、駆け出す。
一刻もはやく、掘り起こさなくては。
手遅れになる前に!



コメント