ひとは、変わっていく。
時が経てば、忘れることもある。
それでも、積み築いた想いは、消えて無くなってしまうわけではない。
ふとした時によみがえる。
あの、雪の下のタイムカプセルのように。
■この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
■ゲーム「風雨来記4」より「母里ちありとのその後」を
題材にした二次小説・ファンアートイラストです。
■当サイト内に掲載している創作物についての不都合等がありましたら、
ページ上部の問い合わせ欄よりご連絡ください。

雪の下のタイムカプセル
<後編>
【前編はこちら】
主な登場人物
キミ:東京から島根の母里家へ婿入りした、フリーのルポライター
リリ:本名は母里ちあり。21歳
【あの夏の終わりに】
遠い昔のような、あるいは、つい昨日のことのような。
あれは、去年の夏の終わり――岐阜から島根の実家へとリリを送り届けたときのことだ。
岐阜の橿森神社から、ざっと500キロ超。
「100キロ程度ならちょっとそこまで」感覚の北海道でも、500となると襟裳岬から宗谷岬までの南北縦断に相当する。
京の都から江戸までを結んだ木曽路、中山道135里とも、ほぼ同距離だ。
今回は、ソロではなくタンデムシートに婚約者を乗せての移動となる。
慎重に、途中途中で休憩しながら約10時間、一日がかりの旅程となった。
当初こそ、彼女の様子次第では途中で列車やバスでの移動に切り替えることも視野に入れていたのだが、そんな心配は何処吹く風と言わんばかり、リリは道中ずっと元気いっぱいだった。
高速の遮音壁が途切れて綺麗な風景があらわれる度に、俺の体にまかれた腕に力がこもる。
背中越しのリリの興奮や楽しげな感情が伝わって来て、俺の方まで嬉しくなった。
そんな二人旅だったからか大きな疲労を感じることもなく、日が落ちきる前にはリリの故郷へと到着。
休む間もなく、リリの両親へ挨拶に伺う。
娘を連れ回していた悪い男じゃないか?と疑われることを心配していたものの、『いつまでたっても帰らなかった娘の首に縄をくくりつけて連れ帰ってきた功労者』として大歓迎されてしまった。
リリを含めた母里一家に強く引き留められ、食べきれないくらいのご馳走をふるまわれた後、今夜は泊まっていけとリリの兄さんの部屋に通されて(このことが原因で後日ちょっとした問題が起こったのだが、その話はまたの機会にしよう)――
すったもんだの一日が終わって倒れるように爆睡した俺に、ようやく落ち着いてリリの故郷の様子を見る余裕が生まれてきたのは、翌日の朝のことだった。
集落のどこかの家で飼われている鶏が、さかんに朝を報せていた。
まだ朝日は山の向こうで、ひんやりとした空気を感じながら、母屋の縁側にリリとふたり、朝霧から沸き立つような山々や青々とした稲穂をたたえる田んぼを眺めていた。
「いいところだね」
「うん」
「ちょっとだけ、種蔵の景色と似てる気がするな」
「うん。そうかも」
「……」
「……」
「来てよかったよ。リリの生まれ育った場所、見られたから」
「これからは、キミの場所でもあるんだよ」
「ああ」
一度東京に帰り、そしてそう遠くないうちに、またこの場所に戻って来て。
それであらためて、この家の、そしてこの土地の人間になる。
『男が女を送るって場合にはな、その女の家の玄関まで送るっていうことよ』とは、映画「男はつらいよ」寅さんの名セリフだ。
旅から旅へ、テキ屋稼業で全国を巡り歩くフーテンの寅さんは、毎度のように旅先で出会ったマドンナに惚れては、失恋したり、自ら身を引いたりして、結局はまた一人旅を続ける。
そんな姿勢を、男の美学、と捉えるファンも少なくないようだ。
そんな寅さんが、長いシリーズの中で、一期一会のヒロインという垣根を越えて繰り返し出会い、時にはひとつ屋根の下で共に暮らすこともあった女性との別れに際して、自ら追いかけて、手を伸ばし、伝えた言葉が先ほどのセリフだった。
あのときの彼の本心は、もしかしたら今の俺と同じだっただろうか。
俺がリリを島根まで送り届けたのは、別に本気で、帰らないんじゃないかと心配したからじゃない。
勇気を出して一歩を踏み出したリリを見て、俺も、俺なりの一歩をリリに向かって踏み出したい、と強く思ったからだ。
独身生活や会社勤めへの未練や不安は無い……と言えば嘘になる。
俺自身の家族にこれからちゃんと話をしないといけないし、仕事も生活スタイルも、これまでとは大きく形を変えることになる。
役所への届け出や手続き、互いの親類へのあいさつ、周囲の人達との新しい人間関係など、結婚に際してやるべきこと、考えるべきことはこれから山のように待ち受けている。
だが、そんな諸々に飛び込んでいくことさえ不思議と楽しげに感じられるのは、リリのおかげだ。
疲れたり、怒ったり、悲しんだりしながら、きっとまた笑い合って、共に前へ進める。
「夫婦」という関係を、リリとなら一緒に楽しんでやっていける、そんな確信が、俺の心の真ん中にし柱のように立っていた。
山の上に太陽が昇り、黄色い日差しが俺達を照らす。
「……」
「…………」
「…………」
沈黙が心地よかった。
どこかでミンミンゼミが鳴き始める。
太陽は見る間に高度を増し、朝靄が波が引くように晴れていく。
俺はふと、目に付いた庭の大木を指さして、
「これ、結構立派だけど、何の木なの? なんだか木の実みたいのたくさんついてるね」
とリリに尋ねると、彼女は、
「りんごだよ」
とこともなげに答えた。
「えっ、りんご?」
驚いて、その木をまじまじと見る。
そう言われてあらためて見るとなるほど、なりは小さいが、確かに形はりんごだった。
結構な数が実っている。ざっと数えても100以上ありそうだ。
「りんごって島根でも採れるんだ」
「どこでもってほどじゃないけどね。飯南の方には大きなりんご園があるし、私の通ってた小学校にもりんごの木があったよ」
「意外だ…」
北海道で収穫されるのは知っていた。
以前、鋭明展の取材の最中に訪れた余市町は、特産品としてりんごを推していた記憶がある。
なんでも、明治時代にりんごが海外から入ってきて栽培が始まったとき、日本で初めて実がなったのが、余市の土地だそうだ。
「そういえば、岐阜にもあったよね。りんご園」
「えぇっ?! そうだっけ」
「お盆明けくらいからかなぁ。
飛騨の道路沿いとか、道の駅とかで袋に入って売ってるの見かけたよ。
高山産!もぎたての地元りんごです!って」
「き、気付かなかった……」
考えて見れば確かに、飛騨や東濃は、信濃国の一部だった時代もあるくらいに長野に近い、日本有数の豪雪地帯だ。
寒冷地に適した果物であるりんごが栽培されていても、まったく不思議はないのか。

それよりも、8月に採れたてりんごが売られていた、という方が驚きだ。
秋から冬のフルーツという印象が強かったけど、夏に採れるものなのか。
スマホを取り出す。
幸い、リリの家の電波の具合は良好だった。
早速ネット検索して調べてみると、品種によるものの、日本のりんごはだいたい8月から早生品種が採れ始めて、11月くらいには晩生品種の収穫が終わるようだ。
スマホをポケットに戻し、再びりんごの木を見上げた。
「このりんご、美味しいの?」
「……うーん。ふつうじゃないかな。
母さんはだいたい、ジュースとかジャムとかお菓子にしてたよ。
東京にいるとき、仕送りと一緒に送ってくれたアップルパイとかタルトはすごく美味しかった」
「なるほど。生よりも、料理向きって感じか」
「そうかも」
りんごジュース。りんごジャム。アップルパイにタルトか。
……うまそうだな。
「……なんだかものすごーく食べたそうな顔してる」
「え、顔に出てた?」
「ふふ、出てる出てる。ん-、熟してるのあるかな。ちょっととってきてあげよっか」
「とってきて……って。……えっ、登るの」
「うん」
言うが早いか、リリはぴょんっと立ち上がって、庭の植木鉢に差してあった園芸はさみを片手に、りんごの木の根元まで歩み寄っていった。
「だ、大丈夫?」
「平気だって。子供の頃からこの木は兄さんと私の遊び場だったんだ。
ほんとは危ないから登るなって言われてたんだけどね」
懐かしそうに語りながら太い枝に足をかけ、そこからは枝から枝へ、細い手足を巧みに使ってあぶなげなく木を登っていく。
「おお……」
実に手慣れたものだ。
青い実ばかりが目立つりんごの群れの中から、熟れた実を物色しているリリ。
木登りの所作からの一連の動作があまりに自然で、野生みのあるしなやかさというか、見ていると、なんだか……
「おとぎ話のさるかに合戦を思い出すな」
つい口から言葉がこぼれ出た。
リリが木の上からこちらへ顔を覗かせる。
真顔で、硬そうな青いりんごを手に持っていた。
大きな丸い目が笑っていない……。
「キミさ、今なんかおもしろいこと言った?」
「い、言ってない言ってない」
「ふーん…………」
じーーーっ……
「ま、いっか」
再びりんごの物色に戻った。
こ、こわい……。
ほんと耳がいいな。
ほどなくして、リリが木を降りてくる。
首の後ろ、フードの中からとれたてのりんごをひとつ、ふたつ、みっつと取り出して、縁側に並べた。
「熟れてるの全然なかったよ。やっぱ収穫期はまだだーいぶ先だね」
赤がひとつ、色づきかけの黄色がひとつ、あきらかに未熟な青がひとつ。
遠目から見た通り、ずいぶん小さなりんごだ。
テニスボールくらいの大きさで、見た目もちょっとごつごつしている。
カメラに収めながら、
「なんて種類なんだろう」
「んー? 昔聞いた気がしたけど、忘れちゃった。
母さんなら覚えてるかな。聞いてくるよ」
「母さーん」と呼ばわりながら台所へと向かうリリを見送る。
……
…………
…………なかなか戻ってこないな。
リリを待っている間に、リンゴの栽培に関する情報をざっと調べてみた。
古くは平安時代から中国由来のリンゴが栽培されていたそうで、これは現在では和リンゴと呼ばれている。
一方、現在俺達が認識しているりんごは西洋リンゴと言って、欧米由来の別物だそうだ。
梨と、西洋なしの違いのようなものだろう。
西洋リンゴは、明治初期に日本に持ち込まれ、わずか二十年足らずで海外へも輸出するほどに日本各地でりんご栽培が大ブームになったという。
だが、直後に害虫や病気が爆発的に蔓延して、青森や長野などを始めとする冷涼な地域(虫や病害が少ない土地)以外の大規模なりんご栽培は、あきらめざるを得なかったという。
一番ひどいときには、ほんの10年の間に、2000ヘクタール(東京ドーム420個ぶん)のりんご園が壊滅したという記録もあるほどだ。
「はーあ……」
疲れた顔をして、リリが戻ってきた。
「ため息なんてついてどうしたんだ」
「朝食の準備、手伝わされそうになったー……。いま、彼と将来について大事な話してるところだから!って言ってなんとかやり過ごしてきたよ。
私もキミも、岐阜からの長旅でまだまだ疲れてるっていうのに、母さんは配慮が足りないんだよね……!」
疲れてる……って、さっきものすごく軽快にりんごの樹に登ってた人の言う言葉なのだろうか。
「なんか申し訳ないな。俺のことはいいから、手伝ってきたら? というか俺も手伝ってこようか」
「えぇ? い、いいんだよ、そんなことしなくて! キミはお客さんで、私の未来の旦那さまなんだから、今日の私はキミが独占!」
リリさん……自分が手伝うのめんどくさいだけでは……いや、あえて言うまい。
「こほん。気を取り直して。
このりんごね、『雪の下』っていうんだって」
「雪の下? 聞いたことがない品種だな」
「私のお婆ちゃんのお婆ちゃんにあたる人が、若い頃北海道とか東北の人と交流があって、そのつてでこのりんごの苗を譲って貰ったみたい」
「お婆ちゃんのお婆ちゃんって言うと、いつくらいの話だろう」
「大昔だねぇ。大正か、もしかしたら明治?」
先ほどりんごについて調べていたサイトで、『雪の下』について何か情報がないか検索してみた。
すると、すぐに答えがあらわれる。
・『雪の下』正式名『ロールスジャネット』。
明治四年にアメリカから日本へ移入された品種である。
・名前の由来は、雪が積もる頃まで収穫がずれ込むことがあるため。
・地域ごとに様々な名前で呼ばれていたが、
明治33年、大正天皇ご成婚にちなんで品種名を『国光』へと統一した。
・『ふじ』が主流になる以前は、100年にわたり日本のりんごの看板種だった。
・貯蔵性が抜群に高く、冷蔵下ならば半年以上保存できる。
・『ふじ』も、『国光』から生まれたかけあわせ品種のひとつで、
高い貯蔵性を強く受け継いでいる。
このりんごの樹の由来がリリの話通りだとすれば、樹齢百年を超える可能性もある。
調べたところ、現在栽培されているりんごの平均的な寿命は50年くらいらしいが、青森には130年超えのりんごの木が現存しているので、全くありえないこととは言えない。
「それでね、もうひとつ面白い話を聞いたよ」
「なに?」
「この木、一本の木に見えるけど、実は並べて植えてた二本の木が、いつの間にかひとつにくっついちゃったんだって」
「へえ」
そう言われて根本の方からよく見れば、幹がふたつ寄り合わさって、ひとつの大きな幹になっている……そういう風に見えなくもないような。
聞いてきたばかりらしい情報を頭の中で整理しているのだろう。
リリは、ゆっくりと言葉を紡ぐ。
「あのね、りんごって、花が咲いたときに、別の木から花粉をもらわないと実がつかないんだって。それで、二種類のりんごの木を隣に並べて植えたんだって」
「なるほど。じゃあ、今、ここになってるりんごは、二種類あるってこと?」
「そうなんだけど、雪の下じゃないほうはほとんど実がつかないみたいで、品種もよくわからないって」
リリが採ってくれたりんごに目をやる。
「じゃあこのりんごは……」
「ぜんぶ雪の下だと思う」
「なあ、リリ。この黄色や緑色のは食べても大丈夫なのか?
明らかに熟してないんだけど」
「大丈夫。……渋いだけで」
「えぇ……渋いのが分かってるのに、なんで採ってきたの」
まさか、さっきのサルカニ合戦のたとえの意趣返しだろうか。
リリはしたり顔で胸を張った。
「あのね、この『渋さ』が体にいいんだよ」
「そうなの?」
「うん。未熟なりんごにいっぱい含まれる成分が、美肌や健康に特別な効果があるんだって。前に何かの雑誌でみたよ」
「そんなの聞いたことないんだが……。からかってない?」
「えーっ。こーんなに可愛い、キミの奥さんの言うことだよ。素直に信じようよー」
「でも、からかってる時の顔してるし」
「えーっ。どんな顔?! そんなことないのに」
疑い半分でまたまたネットを検索してみると、青森りんごの公式ページがトップ画面に出てきた。
――確かに、それらしきことが書いてある。
念のため他にも複数のソースにあたってみると、りんごポリフェノールの抗酸化作用に関する論文がいくつか確認できた。
未熟りんごに多く含まれる有用成分(プロシアニジン)について、大手飲料メーカーなどで積極的に研究されており、肥満対策や疲労回復などに対して一定のエビデンスはあるらしい。
「ほらぁ!」
のぞき込んでいたリリが、どうだと言わんばかりに顔をのぞき込んでくる。
思いのほか距離が近くてどきりとした。
『こーんなに可愛い、キミの奥さん』という言葉を今さら反芻してしまう。
可愛いのは間違いない。
――どちらにせよ、りんご一個二個食べたところで、すぐ健康効果が出るというものでもないだろう。
「ま、気の持ちようってやつかな」
「そうそう気の持ちよう。病は気からって言うし!」
「それはちょっと使い方が違うような」
「ささ、一緒に長ーーーく元気でいられるように、りんごの元気を分けてもらいましょう♪」
他愛もないやりとりを交わしつつ、リリが台所から持ってきていた包丁で三個のりんごをそれぞれ二等分し、二人で分けた。
とりあえず、皮ごと食べてみる。
…………うわ。
青は言うまでもなく、黄色いのもまだまだ硬く、青臭く、そしてものすごく渋かった。口の中が強烈にバサバサする。
ほ、本当に体にいいのか、これ?
隣を見ると、リリは食べかけのりんごを前にこの世の終わりみたいな顔をしていた。
俺も似たような顔をしていたに違いない。
互いに目があい、どちらからともなく笑い転げてしまった。
こういう失敗も、振り返れば良い思い出だ。
りんごの名誉のために、その後に食べた赤く熟れたりんごは、これまでの人生で食べてきた中で、一番美味しく感じたということは明記しておく。
【雪の室】
それからあっという間に月日がたち、いよいよ冬が目の前に迫った頃。
俺もずいぶん母里家に馴染んで、冬野菜の収穫が間近に迫った畑仕事に苦しくも楽しく追われる日々の最中、いよいよ、りんごの木が収穫期を迎えた。
樹上で完熟した赤い果実が鈴なりに実るその様は、まさに、絵に描いたような「りんごの木」だ。
手近な実をとってかぶりつくと、むせかえるような濃厚なりんごの香りと、しゃっきりした触感と、たっぷりの果汁が溢れてくる。
……夏の終わりに食べた時と同じく、いや、それ以上にめちゃくちゃうまい。
いつもの年より絶対美味しい、とリリは何度も言った。
平年より味が良いのは確からしく、お義母さんも、自分たちが結婚した年もすごく美味しかったからそういうジンクスがあるのかも、と本気か冗談か、『新婚夫婦祝福説』を提唱していた。
これから当分、このうまいりんごを好きなだけ食べられるのか、と思うとしみじみとした幸せが湧き上がってきたが、しかし、悠長にはしていられない。
完熟したからには、なるだけ早く全部収穫しちゃおう、とリリは言う。
「このまま木にならしといて、食べるぶんだけその都度採るってわけにはいかないの?」
俺が尋ねると、
「夜は氷点下になるでしょ。木になったまま冷凍りんごになって、それが日差しで溶けたら……」
「腐ってしまうわけか。うわ、そりゃ大変だ」
というわけで、朝夕や仕事の合間を見計らってはリリとりんご狩りに励んで、なんとか本格的な冬に突入する前に、すべてのりんごを採りきることができた。
問題はその後だった。
収穫を終えた俺達の目の前には食べきれないほどのりんご、りんご、りんごの山。
「どうしよっか……これ」
「毎年こんななの……?」
「ううん、いつもはせいぜい50個だって。今年は特別豊作みたい」
「そうなんだ……」
野菜収穫用のコンテナに数杯にわけて、大量に積み上がったりんご。
夏にりんごの木を見たとき100個以上ありそうだな、と思っていたが、とんでもない。
大小合わせてその数じつに683個。
どんなに美味しいといっても、一日に食べられる量には限度がある。
毎日当たり前のように食べていると、当たり外れもあるし、飽きもくる。
母里の親戚とか、俺の実家やお世話になった人に送ったり、義母さんがお菓子作りに使ったりしてもまだまだ余りある。
国道添いの直売所に出そうかという話も上がったが、せっかくなら出来る限り自分達で食べきりたい。
「雪の下」は貯蔵性が非常に高い品種だと言う。
屋内での常温保存でも冬場なら数ヶ月単位で持つそうだが、それはあくまでも腐りにくいというだけで、味や香りは時間経過で抜けていく。
できれば冷蔵保存が好ましい。
しかし、冷蔵庫に入る量にも限度がある。
何か良い方法はないかと考えていると、ふと、以前俺がぐるりの取材で東北を旅した時、りんご農家から聞いた『冬のちょっとした風物詩』の話を思い出した。
「なあ、リリ。このりんごの『雪の下』って名前さ、雪が降る季節まで収穫がずれ込むからこういう名前ってことらしいんだけど」
「うん」
「名前通り、雪の下に埋めるってのはどう?」
「あー…………ああ、なるほど!いけるかも!」
雪室。
雪の多い地域で使われる、食べものの保存技術だ。
保存したいものに藁やビニールなどをかけて、それを雪で埋めてしまうという非常にシンプルな手法。
これは冷蔵庫というより、「保温庫」に近い。
雪は物体を氷温まで冷やすだけじゃなく、空気を大量に含んでいる構造上、高い断熱効果がある。
たとえば外気温が0度より下がった場合は、雪の中は相対的に「暖かく」保たれるわけだ。
おまけに、密閉された雪の中は、真空とまではいかないまでも、空気や微生物の働きも緩やかになるため、保存効率はさらに増す。
青森のりんご農家は、業務用冷蔵庫が発達する以前から、そんな天然の保管庫を使ってたくさんのりんごを貯蔵し、雪が解ける春までの長い期間をかけて出荷していたのだそうだ。
しかし、俺達が雪室作りの検討をはじめてすぐに、大きな問題点が見つかった。
島根は、青森よりも温暖だ。
内陸のこのあたりでは、メートル級の積雪も珍しくないとはいえ、根雪(春先まで残る雪)になるかどうかはその年その年でまちまちらしい。
特に、母里家のある地域周辺は地形の関係か比較的気候が穏やかで、根雪になりにくいのだという。
そのおかげである程度、冬野菜を栽培することができているのでありがたいことなのだが、雪室作りにはちょっと厳しそうだ。
「雪室、良いアイデアだと思ったんだが……難しいか」
「うーん。どっかいいとこあったかなぁ……」
リリは腕を組んで長いこと思案していたが、すぐには思いつかないらしく、俺は俺で、義両親や地域の人たちに聞いたり、ライターのツテを使って調べたりして適した場所を探してみたものの、これまた成果はあがらなかった。
それから数日がたった朝、俺がトイレに入っているときに、ドアがいきなりどんどんと叩かれた。
「あった!あったよ!!」
「うわっ、なんだなんだ?」
ドアごしに、興奮気味の声が飛び込んでくる。
「思い出したよ!
あそこなら、雪室、いけるかも……!」
【よみがえりの果実】
家から畑を挟んで向かいにそびえる山の中腹に、日が当たりにくいせいか毎年春先まで雪の残る洞窟があったはず、というリリの記憶を頼りに、早速その場所を訪れてみた。
「昔来た時は、この中に、いつも四月くらいまで雪が残ってたよ。10年以上前の話だから、今はどうか分からないけど……」
リリと兄さんが「ヨミノイリグチ」と呼んでいたという洞窟。
鬱蒼とした藪に覆われ、山肌に黒々と開くその穴は、なるほど、イザナギとイザナミの逸話に出てくる黄泉比良坂を彷彿とさせる。
入り口は少し縦穴になっていて、そこから雪が入り込んで内部に積もるのだろう。
おそるおそる中に入ってみると、外に比べて気温が数度低い。
数日前に少し降っただけの雪が、多少とけかけてはいるものの今も残っていた。
これは確かに、雪室の長期保存を期待できそうな環境だ。
風土記には「氷室」の地名が記載されていたりするので、少なくとも古墳時代には「雪」や「氷」を能動的に利用した貯蔵法は知られていたようだ。
この洞窟も、もしかしたらリリのご先祖様たちによって、今の俺達と同じような目的で使われていたかもしれない。
数日後、寒波が来て、数メートル先も見えないほどの大雪となった。
あっという間に腰丈の高さまで雪がつもる。
数日経って気候が落ち着くや否や、これがチャンスとばかりにリリと二人で軽バンに大量のりんごを積みこみ、洞窟のある山の麓に乗り付けると、夫婦そろって汗だくになりながら穴の中へ運び込んだ。
洞窟内に大量に積もっていた雪をスコップで掘りわけて室をつくり、ポリ袋で包んだりんごを収め、その上に藁をかければ、あとはもう一度雪をかぶせて、雪室の完成だ。
数時間かけて作業を終えると、上気した顔で夫婦ふたり、笑い合う。
「これで、しばらくは美味しいりんごが食べられるね」
リリが言った。
「ああ。春までの期間限定だ」
「私たちだけのタイムカプセルだね♪」
「ははは。そうだね」
そして、現在――四月。
リリと出会った岐阜の夏から季節は巡って、島根には春が訪れている。
雪室のことを思い出した俺達は、山菜採りからあわてて帰宅し荷物を置くと、洞窟へ急いだ。
あれから何度か訪れてはりんごを持って帰っていたのだが、仕事が忙しくなったり、天気に恵まれなかったりして、ここしばらくはすっかりその存在を忘れてしまっていた。
洞窟へ至る道中の風景は、すっかり春爛漫といった感じだ。
周囲には様々な草木の新芽が伸び、頭上に生い茂る木々の葉は青々と陽光に輝いている。
そこにはすでに、冬の名残など微塵もない。
心配が募る。
はたして洞窟の雪は、りんごは、無事だろうか……
ようやく辿り着いた洞窟に息を切らしながら駆け込むと。
「……よかった」
「うん! ギリセーフだったね!」
雪は解けず、まだ、残っていた。
あと数日遅かったらまずかったかもしれない。
雪室の表面はかなり溶け出して水気を含んでいた。
さながら、みぞれ味のかき氷のようだ。
「……ちょっと美味しそう」
「あはは。シロップもってきたらよかったかな」
「むしろ、この雪も持って帰るの、ありじゃない?」
「え、ほんとに食べる気?」
安心のあまり軽口をたたき合い、この時期までりんごを守ってくれた洞窟に感謝して、俺達は雪室を――タイムカプセルを掘り起こす。
【二人のタイムカプセル】
春の陽気の下、真っ白な雪をまとってきらきらと輝くそのりんご達は、俺の心を心地よく震わせてくれた。
思わずシャッターを切っていると、フレームの奥のリリが、神妙な顔つきでかじりつき、
「…………うん!」
パァッと笑顔になった。
言葉を続けることもなく、夢中でほおばっている。
いつものことながら、実に美味しそうに食べるものだと感心しつつ俺も、りんごの山に手を伸ばした。
リリは、雪室を「タイムカプセル」と言った。
確かに、その通りかもしれない。
今、ここにあるりんごは、夏の。
秋の、そして冬の。
――――過去の俺達からの、贈り物だ。
りんごを長く保管するために、二人で作った雪室。
そこに詰まっていたのは、りんごだけじゃなかった。
嗅覚や味覚は、特に脳との結びつきが強く、記憶に深く残りやすいそうだ。
甘い香りをかぎ、果実を一口かみしめる毎に、今このひとときに至るまでに俺とリリが一緒に過ごした日々が、その時々に感じた新鮮な感情とともに、よみがえってくる。
まだ一年にも満たない、短いようでいて、こうやって振り返ればすでに、数え切れないほどたくさんのエピソードが詰まった、ふたりの旅。
俺達は腰掛けたまま肩を寄せ合い、時間も季節も忘れて、雪まじりのりんごを思い出と共に噛みしめていた。
そうしてどれくらい時間がたった頃だろうか。
はらはらと何かが目の前を通り過ぎて、不意に意識が春へと戻ってくる。
目を向ければ、咲き誇るりんごの花。
二本の幹が、互いに支え合って、一本の大木として立っていた。
100年以上の時を、この二本のりんごの木は寄り添って生き、こうして今も、毎年花を咲かせ、実をつけ続けている。
まるで夫婦のようだ、と思った。
俺達夫婦も、こんな風にありたい。
「ねえ。ちょっといいかな」
リリがそっと言葉を発した。
見ると、綺麗なふたつの瞳が真っ直ぐにこちらを捉えている。
「先日、断るつもりだって言ってた仕事あったよね」
「仲良しカップルのための企画?」
「そうそう、そういうやつ。
あのね……キミの仕事に、私が口出すのはどうかなって思ってるんだけど」
そこまで言って少し言いよどむリリに、俺は口を挟んだ。
「俺としては、むしろ口出して欲しい。リリの言葉で発見することも多いから。もちろん、その上で判断はちゃんと俺自身でするよ」
「そっか。じゃあ、参考意見と言うことで話すんだけど。
あのね、あの話、前向きに検討してみるのもいいんじゃないかなって思う」
「うん」
「向こうの人も、フツーの記事にしたくなくて、キミを選んだのかもしれない」
「うん」
「話してみて、やっぱり合わないなって思ったら、そのときに断ればいいし」
リリはそこまで言うと、真剣な表情を崩して、困ったように笑った。
「なーんて、そういうのは後から考えた理由でね。
ほんとはただ、なんとなく、キミが、やりたそうに見えたんだよね。
……違ってたらごめんね?」
「いや。違わないよ」
「あれれ。すぐに認めちゃうんだ」
少し意外そうな表情。
「ああ。すぐに断らなかったのは、きっとそういうことだと思う。
いつもだったら、自分に合わないと判断した依頼はすぐに断ってたはずなんだ。
なんでかなって自分自身の気持ちと向き合ってみると……
たぶんなんとなく、これって面白い取材になるかもしれないって、心のどこかで感じていたんだと思う」
「…………」
「以前の自分なら確かに、選ばないし、選ばれることもない選択だった。
でも、前の俺は前の俺。今の俺は、今の俺だ」
「うん」
「たとえば、この家の周りだけでも、このりんごの樹もそうだし、タケとササの雑種だとか、由来を知れば縁結びにつながるようなエピソードがいくつも見つかるんだ。
まだまだ知られていない縁結びスポットが、この島根にはきっと、もっと、あるに違いない。
それを探して、巡って、記事にして、そうして記事を見てくれたカップルや夫婦たちが、今度は自分達だけの縁結びの旅をつむげるような。
そんな提案ができれば、面白いんじゃないか、……って」
「うんうん!楽しそう♪」
「今日一緒に山を歩いて、リリといろいろ話をして、あらためて思い知った。
俺一人じゃ見分けることができない、知ることのできない面白いものが、たくさんあるんだ。
だから、リリも色々と力を貸してくれるかな」
「もちろん!」
リリが大きくうなずくと、トレードマークの髪飾りがぴょこんと揺れた。
エピローグ
りんごの花の花言葉は、「選択」らしい。
リリと出会ってから、今日この日まで、たくさんの重要な選択を重ねてきたし、これからも、人生の節目節目で、様々な選択に直面していくことだろう。
夫婦であっても、それぞれ別々の人格、違う価値観を持った一個の人間。
どれだけ愛し合ったとしても、四六時中一緒にいることはできないし、互いの心のすべてを理解し合うことだって不可能だ。
この先、仕事であったり学業であったり、お互い何かしらの夢や目標に向かって進んでいく過程で、もしかしたらいっとき、距離が離れることだってあるかもしれない。
子供ができて、生活リズムや家庭の中での互いの役割が変わっていく中で、夫婦間に深い溝ができてしまう、なんていうのもよく聞く話だ。
――先延ばしにしてしまったのはもしかしたら、リリへの思いやりだけではなく、今のこの心地よい関係が変わってしまうことを恐れる気持ちが、俺自身の無意識の底にあったのかもしれない。
一方で、こうも思う。
かもしれない、かもしれないとまだ見ぬ未来への不安を気に病んでも仕方ない。
未来への不安は裏を返せば、今をこうして一緒に過ごすことができる幸福と、隣にいる存在がかけがえのない相手だということを忘れずにいるための、「縁結びの糸」でもある。
そんな糸を丹念に結び上げていけば、この先もしも、旅路の途中で二人が行き先に迷ってしまうようなことがあった時、確かな道標になってくれるだろう。
今日、掘り起こした雪室のように。
タイムカプセル。
心の中にしまわれたたくさんの感情や思い出を、時間を超えて呼び覚ますもの。
もしかしたら、俺の旅や、写真や、記事もまた、俺とリリの、あるいは誰かと誰かにとっての、そんな『タイムカプセル』となり得るかもしれない。
それはきっと――――最高だ。
「キミといっしょに、このりんごのお花を見られてよかった」
リリがそっとささやいて微笑み、俺の方に真っ直ぐに向き直って、ふかぶかとお辞儀した。
「これからも、末永くよろしくお願いします」
こちらも背筋を伸ばしてお辞儀を返す。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
そう言って、二人で微笑み合った。
なんだか無性にリリを撮りたくなって、意識するより前にカメラを彼女に向けていた。
何かポーズをとることもなく、自然体のままそこにいる。
心が通じ合う、というのはこういう瞬間のことを言うのかもしれない。
今日の俺達の、最高の場所。
最高に満たされた場所。
けれどそこで足を止めることなく、また、次の最高の場所を求めて、これからもいつまでも、一緒に歩き続けていきたい。
そんな想いとともに写し撮った、一枚。
これは、長い長い二人旅を続けていくための――今の俺達から、未来の俺達への、贈り物だ。
リリは花がほころぶように笑っている。
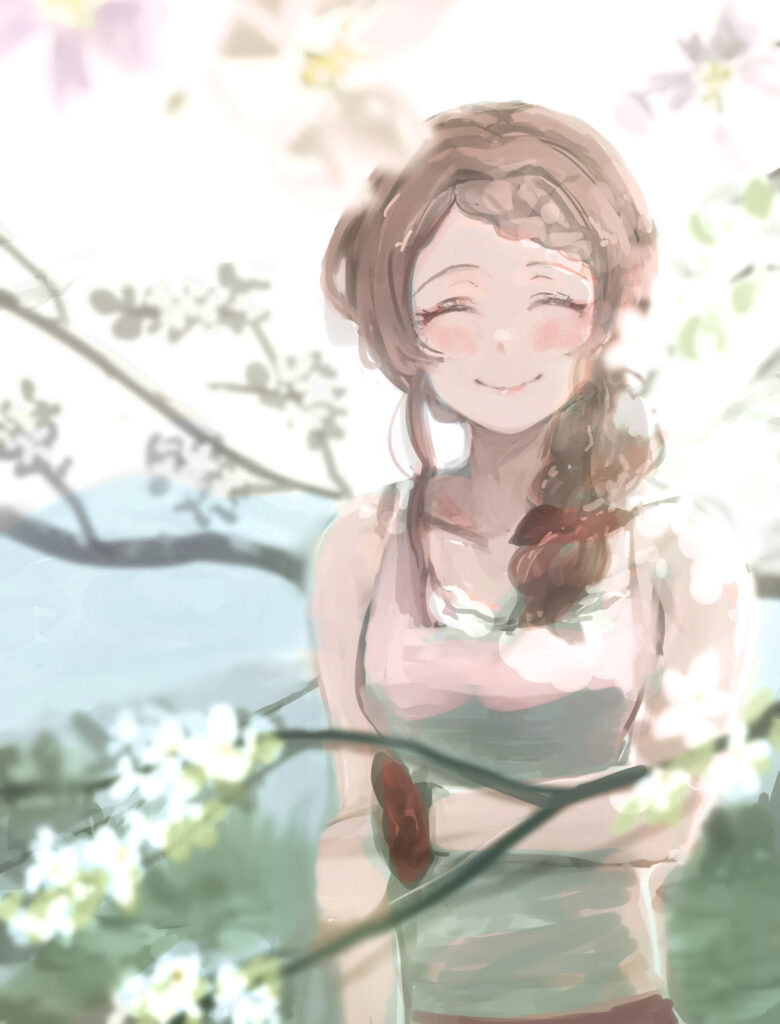
雪の下のタイムカプセル
了



コメント